「パーキンソン病」は手の震えなどの運動症状・便秘などの非運動症状が現れる神経変性疾患です。
高齢になるほど発症率が高いため、今後患者はさらに増加するとみられています。
この記事では、パーキンソン病に特徴的な顔つきや、それ以外の主な症状、治療法を解説します。
治療法のひとつとして、症状の改善効果が期待できる「ストレスフリー療法」も紹介。
パーキンソン病の症状に興味がある方や、ご本人やご家族がパーキンソン病の方にも、おすすめの内容です。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン病とは一体どんな病気なのか

「パーキンソン病」とは、「振戦(震え)」「筋固縮」「動作緩慢」「姿勢反射障害」を主な運動症状とする進行性の病気です。
50歳以上で発症することが多い病気ですが、40歳以下で起こることもあり「若年性パーキンソン病」と呼ばれます。
高齢になるほど発症率が高く、65歳以上では100人に1人程度です。2021年度の調査から、日本での患者数は約20万人と推定。
運動の制御に関わる神経伝達物質「ドパミン」は、中脳の「黒質」にあるドパミン神経細胞で作られます。
パーキンソン病になるとその神経細胞が減少し、ドパミンが十分に作られなくなります。
その結果、運動の調節がうまくいかなくなり、体の動きに障害が現れるのです。
パーキンソン病になると現れる顔つき

パーキンソン病になると、特徴的な顔つきが現れることがあります。
パーキンソン病患者に見られることが多い顔つきは、「仮面様顔貌」と「脂漏性顔貌」の2つです。
以下、それぞれについて詳しく解説します。
仮面様顔貌
「仮面様顔貌」とは、顔の表情が乏しくのっぺりとした印象になる症状です。
これは、顔の筋肉の固縮や動作緩慢、自律神経の異常、精神的な症状などが原因とされています。
具体的な症状は、以下のとおり。
- 顔の筋肉がこわばり、喜怒哀楽などのさまざまな表情をすることが難しい
- まばたきが減少し、目が大きく開いたままになる
- 口角が下がる
- 声が小さく、抑揚のない単調な話し方になる
- 口をしっかり閉じられず、よだれが増える
脂漏性顔貌
「脂漏性顔貌」とは、顔が脂っぽくなる症状です。
これは、自律神経の障害により、顔面や頭皮の皮脂の分泌が過剰になることが原因とされています。
パーキンソン病では、脳内の神経伝達物質であるドパミンの減少により、自律神経系にも影響が出ます。
これにより、皮脂腺の活動が亢進することで脂漏性顔貌が引き起こされるのです。
皮脂の過剰分泌は、脂漏性皮膚炎という皮膚疾患を引き起こすことも。
症状は、赤みやフケ、かゆみなどです。
顔つきの変化以外に見られるパーキンソン病の主な症状
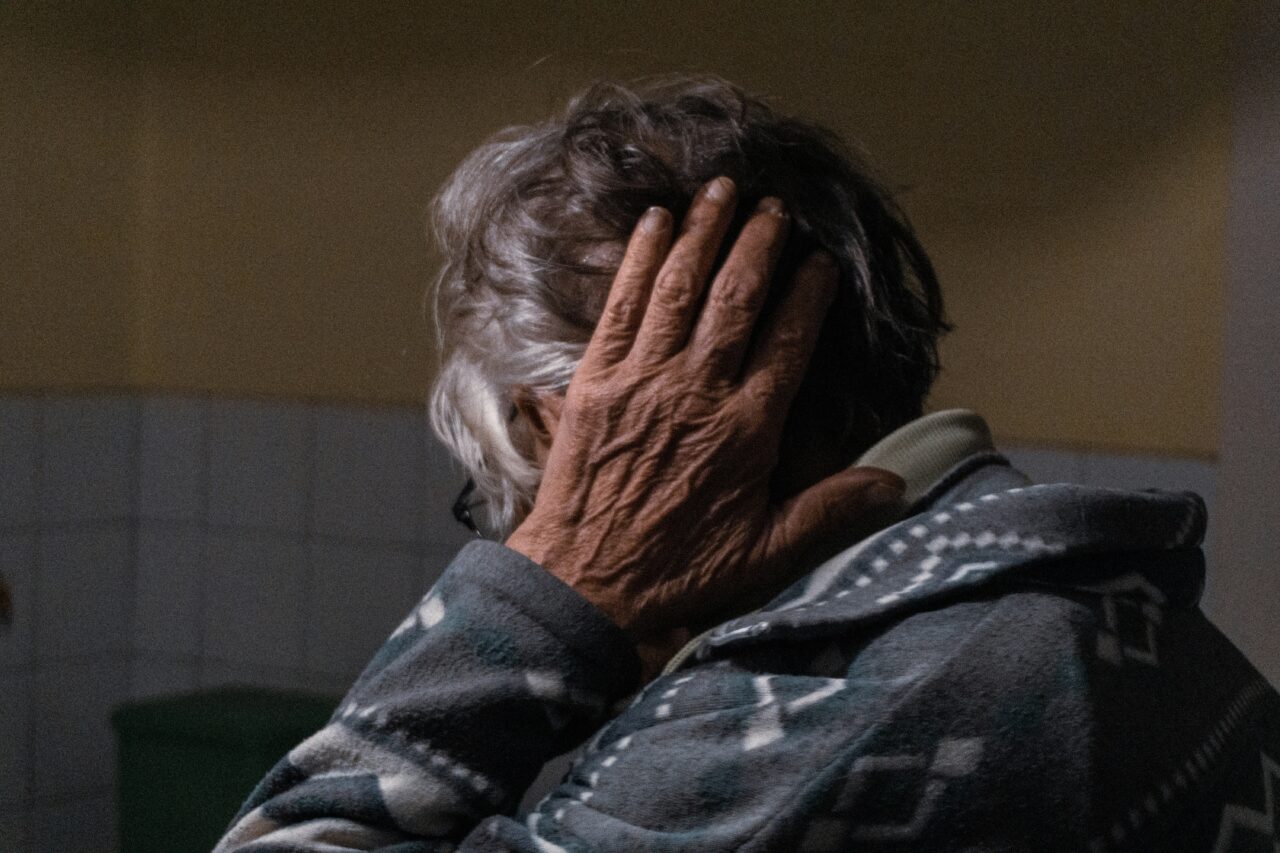
ここでは、顔つきの変化以外のパーキンソン病の主な症状を紹介します。
振戦、筋固縮、動作緩慢、姿勢反射障害の4つが代表的な運動症状です。
最初の3つはパーキンソン病の発症初期から見られます。
それら以外にもさまざまな症状が見られますが、ほかの病気が原因のこともあるので注意が必要。
振戦
「振戦(安静時振戦)」とは、何もしないでじっとしているときに、手などが小刻みに震える症状です。
手の場合は、いすに座って膝に置いているときや歩いているときなど力を入れていないときに起こり、動かすと震えは小さくなります。
一般的に、以下のような特徴がみられます。
- 通常は片方の手で起こる
- しばしば、親指と人差し指をこすり合わせる動作がみられる(丸薬丸め運動)
- 手を意図的に動かしているときにはあまり起こらない
- 睡眠中は震えが治まるが、目が覚めると震えが始まる
- ストレスや疲労によって悪化することがある
- 進行すると、もう一方の手や足にも起こるようになる
筋固縮
「筋固縮(筋強剛)」とは、筋肉がこわばり、身体がスムーズに動かなくなる症状です。
パーキンソン病の筋固縮は自分では気づきにくいのですが、他者が患者の腕や足を動かそうとすると、関節がカクカクするような抵抗が感じられます。
肘や膝、手首などの関節に、持続的なこわばりや抵抗を認める筋固縮が「鉛管様固縮」。
それに対し、他者が関節の曲げ伸ばしを行った際に、歯車のような抵抗を認める筋固縮を「歯車様固縮」といいます。
筋固縮が進行するとスムーズに体を動かせず、歩行や運動も困難になり、顔面の筋肉にも影響が及ぶのです。
動作緩慢
「動作緩慢(無動・寡動)」とは、動きが遅くなり、同時に細かい動作がしにくくなる症状。
動きが遅く小さくなり、動作の開始が困難になります。
そのため、患者はあまり動かなくなって、関節が硬くなり筋力が低下するため、動くことがますます難しくなっていくのです。
これに関連した症状としては、以下のようなものがあります。
- 話し方に抑揚がなくなり声が小さくなる
- 寝返りを打てなくなる
- 歩くときに最初の一歩が出にくくなる(すくみ足)
- 書く文字が小さくなる(小字症)
- 飲食物を飲み込みにくくなる(嚥下障害)
姿勢反射障害
「姿勢反射障害(姿勢保持障害)」とは、バランスが悪くなり転倒しやすくなる症状です。
この症状は、パーキンソン病の初期には見られず、進行してから現れます。
高齢者の場合、転倒により骨折し、そのまま寝たきりになることもあるため、注意が必要。
一般的に以下の症状が見られます。
・姿勢が前かがみになる
・体のバランスがとりにくくなり、転びやすくなる
・歩いていて止まれなくなる、方向転換をするのが難しい
・首が下がる、体が斜めに傾く
起立性低血圧
「起立性低血圧」とは、急に立ち上がったときなどに、めまいや立ちくらみ、眼前暗黒感、失神などを起こす症状です。
通常は、身体を起こすなど体勢の変化を感知すると、脳への血流を維持するため血圧を上げるように指令を出します。
パーキンソン病の原因となる異常なタンパク質が自律神経に関わる末梢神経にも蓄積し、その指令が十分に伝わらず、立ちくらみやめまいを引き起こすことになるのです。
仰臥位または座位から立位への体位変換の際、起立3分以内に以下のいずれかが認められた場合に診断されます。
特に症状として失神がみられる場合は、生活の質が著しく低下し、転倒によるけがのリスクもあるため、早急な対応が必要。
- 収縮期血圧が20mmHg以上低下
- 収縮期血圧の絶対値が90mmHg未満に低下
- 拡張期血圧が10mmHg以上低下
嚥下障害
「嚥下障害」とは、飲食物を口に入れ噛んで飲み込むまでの「嚥下」の動作のどこかに問題があり、うまく飲み込むことができない症状。
原因は、口の周りにある咽頭筋の動作が遅くなっていることです。
運動機能の低下や薬の影響が関係していると考えられています。
一般的に、以下のような特徴がみられます。
「誤嚥」により「誤嚥性肺炎」を引き起こすと、命に関わることもあるので特に注意が必要です。
- 食事に時間がかかる
- 食べものや飲みものがつかえる、むせやすい
- 唾液が口のなかにたまりやすい
- 食べものが口のなかに残る
- 飲み込んだものが気管に入る(誤嚥)
便秘
「便秘」とは、便通が3日以上なかったり、便が硬くて量が少なく残便感があったりする症状です。
パーキンソン病では初期から現れ、90%以上の患者にみられるとされています。
これは、腸の蠕動運動を司る自律神経の働きが低下し、腸の動きが鈍くなることが原因。
また、パーキンソン病の治療薬や日常生活の活動量低下、排泄にかかわる筋力の衰えなども便秘を悪化させる可能性があります。
便秘の症状を改善するには、食物繊維の多い食事を心がけ、水分を十分に摂取し、適度な運動をすることが大切です。
排尿障害
パーキンソン病における「排尿障害」は、頻尿・尿失禁・排尿困難・尿意切迫感などで、患者の6割以上でみられる症状です。
特に、夜間頻尿が多くみられるという特徴があります。
自律神経の障害により、膀胱の機能が制御できなくなることが原因。
また、薬の副作用により排尿困難が生じることもあります。
頻尿ではトイレに行く回数が増えますが、運動機能の低下や焦る気持ちから、転倒などの事故のリスクが高いため注意が必要です。
また、失禁により精神的なダメージを受けたり、不安から外出を控えたりすることにもつながります。
パーキンソン病の治療法

パーキンソン病の治療は、「薬物療法」が基本です。
しかし、薬を一定期間以上服用している患者で特定の症状がみられる場合などには、「手術」が行われることがあります。
ここでは、パーキンソン病の治療法で一般的な「薬物療法」と「手術」に加え、「ストレスフリー療法」について解説します。
薬物治療
パーキンソン病の原因は脳のドパミン欠乏なので、治療は薬によりドパミンの働きを補うことが主体です。
以下に代表的な2剤を紹介します。症状や進行度に合わせて、これらの薬や他の薬を組み合わせて使います。
① レボドパ(L-dopa)
脳内でドパミンに変化して作用します。
治療効果が高く、速効性に優れているのが特徴ですが、作用時間が短いことが欠点です。
② ドパミンアゴニスト
ドパミンに似た作用をもつ薬。
治療効果がやや弱いのですがゆっくり効くので、1日1回の服用で安定した効果を得られます。
レボドパに比べ、悪心や低血圧などの副作用が出やすいのが欠点です。
手術
薬物療法の副作用が強かったり、症状のコントロールが難しかったりする場合には、手術が選択されることがあります。
現在主流となっている「脳深部刺激療法」は、脳の奥のドパミンに関係する部位に電極を埋め込み、弱い電気刺激を与えることで、症状を抑える治療法です。
特に、「視床下核刺激術」が多く行われます。
手術によりパーキンソン病が完治することはありません。
症状をコントロールし、リハビリテーションも行いながら、生活の質を向上させることが目的です。
ストレスフリー療法
「ストレスフリー療法」とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30~60分照射する温熱療法です。
これにより、全身の血流や自律神経を整え、高血圧や糖尿病、認知症、不眠症、冷え症、白内障など、さまざまな病気の予防・改善効果が期待できます。
また、ストレスフリー療法により、パーキンソン病の症状が大きく改善した実例が報告されています。
当療法に特化した専門クリニックとして信頼されているのが、「銀座数寄屋橋クリニック」です。
公式サイトにてさらに詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ

今回は、パーキンソン病で見られる特徴的な顔つきなどの症状や治療法を解説しました。
パーキンソン病では、「仮面様顔貌」や「脂漏性顔貌」という顔つきが現れることがあります。
それ以外の症状は、「振戦」「筋固縮」「動作緩慢」「姿勢反射障害」といった運動症状や、「便秘」「排尿障害」などの非運動症状などです。
治療法は、「薬物療法」が基本で、場合によっては「手術」が選択されることも。
また、パーキンソン病の症状を改善する効果が期待できる「ストレスフリー療法」もあります。
この記事が、パーキンソン病の症状や治療法についての理解の一助になれば幸いです。






