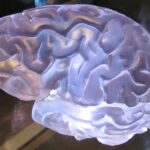40代以降に増えるパーキンソン症候群。
寿命や進行に不安を感じる方も多いでしょう。
そこで今回は、5つの症状や治療法、進行を緩やかにするポイントをわかりやすく解説。
体に優しいストレスフリー療法の選択肢もご紹介していきます。
パーキンソン症候群の軽減に役立つ方法もご紹介していくので、ぜひ参考にしてください。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン症候群とは一体どんな病気なのか

パーキンソン症候群は、パーキンソン病に似た症状を引き起こす神経の病気です。
手足の震えや動作の緩慢、姿勢の崩れなどの症状が現れますが、進行の仕方や治療法は異なるいくつかのタイプがあります。
日常の生活に影響を与えることもあるため、注意が必要です。
パーキンソン症候群に早期に気付いて、適切な対処をするのがとても大切。
パーキンソン症候群の寿命

パーキンソン症候群には、主に5つの疾患があります。
進行性核上性麻痺・多系統萎縮症・大脳皮質基底核変性症・正常圧水頭症・脳血管障害です。
そこで、パーキンソン症候群の寿命を詳しく解説していきます。
それぞれの特徴や進行、治療の選択肢を知り対策につなげましょう。
進行性核上性麻痺
発症後、個人差がありますが、平均余命は発症から5年から9年程度が一般的。
名前のとおり進行速度は速く、数年で寝たきりになり日常生活に大きな影響を与える難病です。
発症後、徐々に進行していくのが、歩くときにふらついたりする歩行障害は、転倒のリスクが高まります。
他には、眼球運動障害、構音障害、嚥下障害、認知機能障害などもあり、これらの症状は、根本的な治療法がないのが現状です。
ですが、症状緩和に治療やリハビリをおこないます。
少しでも安心して日々を過ごすためには、症状の理解と、適切な医療や介護支援を早めに受けることがとても大切です。
多系統萎縮症
多系統萎縮症は、主に中枢神経と自律神経に影響を与え、緩やかですが確実に進行していく神経変性疾患です。
一概に余命を予測するのは困難で、経過は個人差があります。
平均余命は、診断のあと5年から9年ほどです。
多系統萎縮症の一般的な経過を詳しく見ていきましょう。
(経過と余命)
- 発症から約3年:歩くときにふらつきが増え、介助が必要になることがあります
- 発症から約5年:車椅子での移動が中心になる方もいます
- 発症から約8年:寝たきりで過ごす時間が長くなっていきます
- 発症から約9年:多くの方が命を落とす可能性があるといわれています
多系統萎縮症は進行する病気ですが、早期から医療や介護の支援を受けると、安心して過ごせます。
訪問リハビリなどを上手に活用しながら、生活の質を大切にしたサポートが可能です。
大脳皮質基底核変性症
大脳皮質基底核変性症は、ゆっくりと進行する神経の病気で、症状の現れ方や進み方には個人差があります。
発症後6年から8年ほどかけて少しずつ症状が進行し、初期には手足の動かしにくさや震えが見られるのが特徴です。
やがて歩行や会話にも影響が及ぶようになります。
寿命については明確なデータが少ないものの、最終的には寝たきりとなり、予後はあまりよくありません。
主な死因は誤嚥性肺炎や栄養不良などで、嚥下機能の低下によるものです。
進行を止める治療法はありませんが、症状緩和のための対症療法に薬が用いられることもあります。
日常の生活に支障をきたすようになるまでには、ある程度の時間があり、適切なサポートにより穏やかな生活を保つのも可能です。
不安を感じた際には、医療機関などに早めの相談をおすすめします。
正常圧水頭症
正常圧水頭症は、脳室に過剰な脳脊髄液がたまり、さまざまな症状を引き起こします。
歩行障害や認知機能の低下、尿失禁があり、多くが高齢者に見られる症状で、パーキンソン症候群の一因となる場合も。
早期の診断での適切な治療、主にシャント手術を受けると、期待できる希少な疾患のひとつです。
寿命への影響も他の神経変性疾患と比較すると軽度で、治療によって日々の生活を大きく改善できる可能性があります。
少しでも不安を感じたときは、早めの受診がとても大切です。
脳血管障害
脳血管性パーキンソニズムは、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害によって、パーキンソン病に似た症状が現れる状態です。
特徴は、筋肉のこわばりや歩行障害で、特に下半身に症状が強く出ることがあります。
人により症状の進行は異なる症状ですが、適切なリハビリ・介護により、生活の質を保つことも可能です。
寿命には、脳血管障害そのものの再発のリスクや、他の合併症の影響が関わることもあります。
そこで大切なのが、定期的な受診や生活習慣の見直しです。
不安な気持ちがある方は、医師や介護スタッフに相談することから始めてみましょう。
また、ひとりで悩みを抱え込まないよう、ご家族の理解と支えも安心につながります。
パーキンソン症候群の治療法

パーキンソン症候群には、薬物治療や手術、運動療法、職業療法、言語療法、カウンセリング、ストレスフリー療法があります。
ご自身に合った医療や介護支援を受けることで、少しずつでも安心して生活を続けられます。
そこで、それぞれの治療法を、詳しくご紹介していきます。
薬物治療
パーキンソン症候群の薬物治療は、主に症状の緩和を目的におこなわれます。
治療方針は、原因となる疾患により異なる治療方針です。
多くの場合、共通してドパミンの働きを補う薬が使われます。
特にパーキンソン病では、L-ドパ製剤やドパミンアゴニストなどが治療の中心となり、期待できるのが運動機能の改善です。
一方で、進行性核上性麻痺や多系統萎縮症などでは、同じ薬でも効きにくいこともあり個別の対応が求められます。
必要なのは、症状や進行スピードに応じて薬の種類や投与量を見直していくことです。
薬の選択肢や投与量の調整は、副作用や日常生活の影響も考慮し一人ひとりの体の状態を医師とよく相談し慎重に調整していきます。
手術
パーキンソン症候群の症状が、薬だけでは十分にコントロールできない場合、外科的な治療が選択肢となることもあります。
例えば、MRガイド下集束超音波療法(MRgFUS)は、頭を切らずにおこなえる新しい治療法です。
MRIで脳の状態を確認しながら、超音波で特定の部位にアプローチすることで手の震えなどの症状改善が期待されます。
症状の種類や進行の度合い、日常生活への影響などによって適応は異なるため、医師との相談が大切です。
手術と聞くと不安になるかもしれません。
ですが、安心して治療に臨めるよう、事前に十分な情報を知っておくことも大切です。
運動療法
パーキンソン症候群の運動療法は、身体機能の維持と改善するための大切な取り組みです。
ストレッチや筋力トレーニングは筋肉の柔軟性を保ちます。
また、バランス感覚や歩行機能の向上にもつながり、運動障害の管理にとても重要です。
これらは、日常生活のなかで感じる運動の困難さを軽減し、症状の管理にも役立ちます。
継続的な運動は気分の安定、睡眠の質の向上にもつながり、生活全体の質を高めてくれるのもよい点です。
無理のない範囲で取り組みましょう。
理学療法士など専門家のアドバイスを受けながらおこなうと、より安全で効果的です。
パーキンソン症候群に向き合ううえで、運動療法は日々の積み重ねが変化を生む力となります。
職業療法
パーキンソン症候群の職業療法とは、ご自身が自分の家や職場で無理なく過ごせるように環境や動作の工夫を重ねていく支援です。
動作のしやすさや、安全性を高めることで、少しずつできることを増やしていくことを目標にします。
例えば、よく使う道具を手に取りやすい位置に置いたり、転倒予防に滑りにくいマットを使うなどです。
今できることを活かしながら、少し頑張ればできることを増やしていくことも大切なポイント。
なので、日々の作業手順を一緒に見直し、その方のペースに合わせ取り組むようにしましょう。
言語療法
パーキンソン症候群では、声が小さくなったり、滑舌が悪くなる話しづらさが現れることがあります。
また、飲み込みにくさ(嚥下障害)が見られることもあり、日常生活に不安を感じる方も少なくありません。
そこで、このような症状がある場合、言語療法士によるトレーニングがおこなわれることがあります。
言語療法でおこなうのは、声の出し方や発音、飲み込みの練習などです。
安心して会話や食事ができるよう支援をしていきます。
大切なのは、その方の状態に合わせ無理のない範囲で進めることです。
毎日の暮らしが少しでも心地よく過ごせるよう寄り添う支援や、家族や周囲の方とのコミュニケーションをサポートします。
カウンセリング
パーキンソン症候群では、気持ちが不安定になったり、孤独感や落ち込みを感じることがあります。
不安の多くは、症状の変化や将来への不安の影響からです。
このような心の揺らぎに対し、公認心理師や臨床心理士による認知行動療法(CBT)などのカウンセリングが心の支えになります。
期待されているのは、不安や抑うつの軽減、睡眠の改善やストレス対処力の向上です。
また、患者同士の共有も孤独感の軽減となり役立ちます。
心の安定と生活の質を少しずつ取り戻し、大切な時間となるカウンセリングは患者さんにとって大切な役割です。
ストレスフリー療法
パーキンソン症候群の症状に向き合いながら少しでも快適な毎日を送りたい方に、ストレスフリー療法の選択肢があります。
薬に頼らず、体に優しい温熱刺激でストレスを緩和し、血流を促進させるケアです。
直径3ミリの導子を4つの特定のツボに装着し、リズミカルで自律神経のバランスを整えることが期待できます。
遠赤外線による温熱刺激を30分から60分与える療法は心と体の両方に寄り添います。
治療を受けることは大切ですが、補助的なアプローチとして、心や体への優しいケアを取り入れてみるのもひとつの方法です。
「銀座数寄屋橋クリニック」はストレスフリー療法に特化していします。
公式サイトにて、さらに詳しい情報をご覧いただけます。
パーキンソン症候群の症状を軽減することが重要

パーキンソン病症候群は根本的な治療法がないため、症状をやわらげながら、少しずつ生活の質を高めていくことが大切です。
症状を軽減するための方法としては、無理のない運動療法や、意識した食事があります。
また、疲労感の軽減や生活の質の向上となるのが、十分な休息や睡眠の確保です。
さらに、症状の進行を穏やかにする正しい薬の服用や、定期的な診察で専門医との連携なども重要。
ストレスを溜めない工夫や、趣味を持つことも症状の安定につながります。
まとめ

パーキンソン症候群は、進行の仕方や治療法が異なる5つの疾患があります。
症状を軽減することが重要なため、薬物療法や運動療法、カウンセリングなどを組み合わせた継続的なケアが大切です。
定期的な診察で、主治医に分からないことを質問し、治療に関する疑問を解消しましょう。
また、心と体をやさしく整える「ストレスフリー療法」を補助的に取り入れる選択肢もあります。
パーキンソン症候群の早期治療を心掛けてください。