パーキンソン病では「振戦(手足の震え)」は代表的な症状のひとつです。
パーキンソン病は、振戦などの運動症状や、便秘などの非運動症状が現れる神経変性疾患。
高齢になるほど発症率が高いため、今後患者はさらに増加すると見込まれます。
この記事では、パーキンソン病でなぜ振戦が起きるのか、パーキンソン病以外の振戦との見分け方、振戦の治療法などを解説します。
ご自身やご家族がパーキンソン病の方、振戦という症状について知りたい方に、おすすめの内容です。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン病とは一体どんな病気なのか
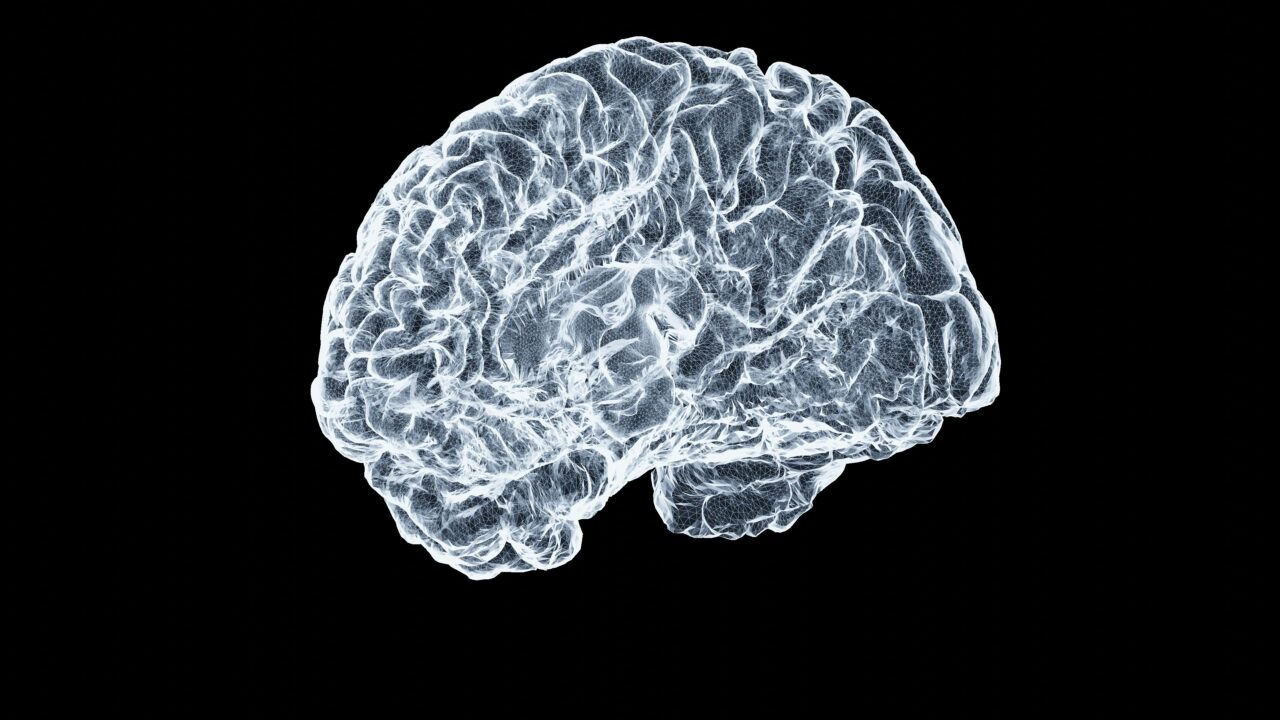
「パーキンソン病」とは、手足の震えや筋肉のこわばりなどの症状が現れる進行性の病気です。
多くは50歳以上で発症しますが、40歳以下で起こることもあり「若年性パーキンソン病」と呼ばれます。
高齢になるほど発症率が高く、65歳以上では100人に1人程度。
この病気は、脳の神経伝達物質ドパミンを産生する神経細胞が減少することで発症します。
ドパミンは主に運動の調節を司るため、その不足は身体のさまざまな運動障害を引き起こすのです。
パーキンソン病でなぜ振戦が出現するのか

パーキンソン病の主な症状のひとつに、「振戦(安静時振戦)」があります。
振戦とは、何もしないでじっとしているときに手などが小刻みに震える症状です。
手の場合は、いすに座って膝に置いているときなど力を入れていないときに起こり、動かすと震えは小さくなります。
パーキンソン病では、脳の神経細胞の中に「αシヌクレイン」というタンパク質が蓄積して、「レビー小体」と呼ばれる凝集体を形成。
レビー小体が中脳の「黒質」に蓄積すると、ドパミン神経細胞の脱落・変性が引き起こします。
ドパミンは、運動の調節に関わる神経伝達物質であり、その減少により身体の動きに障害が現れるのです。
パーキンソン病は進行性の病気であることに注意

パーキンソン病は進行性の病気です。
進行するにつれて生活の質が低下するため、早期の発見と治療開始が重要。
初期には、身体の片側に軽度な「振戦(ふるえ)」や「筋固縮(筋肉のこわばり)」、「無動(動作が遅い)」などの運動症状が見られますが、日常生活に大きな支障はありません。
中期には、症状が左右に広がり、歩行障害や転びやすくなる「姿勢反射障害」が現れます。
日常生活の一部に介助が必要になる段階です。
末期には、食事・排泄・入浴などの日常のすべての動作に介助が必要。
寝たきり状態となるケースも多く、さらに呼吸障害や精神症状、認知症の進行なども見られます。
特に、嚥下障害による誤嚥性肺炎に注意しなければなりません。
パーキンソン病以外の振戦とは一体何か

振戦には、パーキンソン病で見られる安静時振戦以外にも、いくつかの種類があります。
正常なもの(生理的振戦)や、病気や薬剤などが原因のもの(企図振戦など)です。
以下、生理的振戦と企図振戦について解説します。
生理時振戦
「生理的振戦」とは、誰にでもある程度みられる正常な振戦です。
例えば、手をいっぱいに広げたままにすると手の筋肉がかすかに震えます。
このような震えは、筋肉が神経によって精密に調節されているために現れる現象です。
たいていはほぼ気にならない程度の振戦ですが、例えば以下のような状況では顕著に現れることがあり、不安になる人も。
- ストレスや不安を感じているとき、睡眠不足のとき
- 飲酒や鎮静薬の使用をやめたとき
- カフェインを摂取したとき
- 特定の薬剤を使用したとき
- 甲状腺の機能が亢進しているとき
企図振戦
「企図振戦」とは、机の上のペンに手を伸ばしているときなど、意図的な動作の最中に起こる振戦です。
対象物に近づくほど振戦は悪化し、手の震えにより対象物が取れないこともあります。
比較的ゆっくりとした粗大な動きです。
企図振戦は、バランス感覚と協調運動を司っている小脳の障害(脊髄小脳失調症、多発性硬化症など)によって起こると考えられています。
その他、脳卒中や腫瘍、アルコール使用障害、鎮静薬・抗てんかん薬の乱用などにより、小脳の機能不全が引き起こされ、企図振戦が生じる可能性も。
パーキンソン病の振戦とそのほかの振戦を見分けるポイント

振戦の症状が見られた場合に、それがパーキンソン病によるものかそれ以外の原因によるものか、見分けることは重要です。
以下、パーキンソン病の振戦と、原因が不明な「本態性振戦」について、それぞれの特徴を示します。
① パーキンソン病の振戦
- 手や足に好発
- 家族歴はほとんど見られない
- 振戦以外に筋固縮や無動などの症状も
- 安静時に出現(遅い震え)
- 食事などの動作は遅いが震えは小さい
- 書く文字が小さくなる(小字症)
② 本態性振戦
- 手や頭、声に好発
- 家族歴が見られることが多い(家族性振戦)
- 症状は振戦のみ
- 姿勢時や動作時に出現(速い震え)
- 震えにより食事などの動作がうまくできない
- 書く文字は大きく乱れる
パーキンソン病の振戦による影響

パーキンソン病により振戦の症状がみられる場合には、どのような影響があるのでしょうか。
症状が進行すると、振戦以外の症状も顕著になり生活の質が大きく低下するため、周囲の身体的・精神的サポートも必要です。
ここでは、「日常生活に対する影響」「社会的な影響」「心理的な影響」について解説します。
日常生活に対する影響
パーキンソン病の振戦が最も直接的に影響を及ぼすのは日常生活、特に細かい運動制御を必要とする活動です。
例えば以下のような影響が出る可能性があります。
①食事
- 飲食物をうまく口に運べず食べこぼしが増える
②着替え
- ボタンをかけたりファスナーを上げたりするのが難しくなり、着替えに時間がかかる
③書字
- 文字が震えて読みにくくなる
- 字が小さくなる
- 書くことが困難になる
④歩行
- バランスを崩しやすくなる
- 歩幅が狭くなる
- 歩行がぎこちなくなる
社会的な影響
パーキンソン病の振戦は、社会的な影響を及ぼす可能性も。
周囲に人がいる状況で振戦の症状が現れると、恥ずかしさや他人からの好奇の視線から、外出を控え社会的なつながりを避けるようになることがあります。
すなわち、社会的に孤立するようになり、ボランティアなどの社会活動や趣味の集まりなどへの参加の意欲も減退します。
生活の質の低下につながる可能性がある点に注意しなければなりません。
この問題を解決するには、社会全体のパーキンソン病に対する理解を高めることが必要です。
心理的な影響
パーキンソン病の振戦は、重大な心理的影響をもたらすことがあります。
振戦により今まで容易にできた動作や作業ができなくなると、フラストレーションや恥ずかしさ、無力感を引き起こす可能性があるのです。
それにより、精神症状を引き起こすことも。
また、振戦による身体的な不快感やストレス、不安のために睡眠障害を起こすこともあります。
睡眠不足はパーキンソン病の症状をさらに悪化させることにもつながるので、注意が必要です。
パーキンソン病の振戦に対する治療法
パーキンソン病の治療は、主に治療薬「レボドパ」を用いる薬物療法とリハビリの組み合わせが基本です。
場合によっては「脳深部刺激療法」などの外科手術が行われます。
また、特に振戦に対する治療には、「抗コリン薬」や「FUS」が用いられる場合も。
ここでは、この2つの治療法について解説します。
抗コリン薬
パーキンソン病の振戦の治療に「抗コリン薬」が用いられることがあります。
脳内神経伝達物質のアセチルコリンとドパミンは、互いに拮抗し合っています。
パーキンソン病でドパミンが不足すると、アセチルコリンの作用が強くなる点に注意が必要。
抗コリン薬でアセチルコリンの働きを抑えることで、ドパミンの作用を強めます。
「トリヘキシフェニジル製剤(アーテン)」が、パーキンソン病の振戦治療での代表的な抗コリン薬です。
ただし、抗コリン薬の使用により、口渇や吐き気、便秘、口内炎、視力異常、排尿障害などの副作用が出現することがあります。
FUS
パーキンソン病の振戦の治療に「MRガイド下集束超音波治療(FUS)」が行われることもあります。
これは、MRI画像を用いて、脳深部にある振戦の神経活動が異常な部分に、超音波のエネルギーを集中させて照射し熱凝固する治療法です。
頭部の切開・穿孔や脳への電極刺入、放射線被曝などがなく、患者の身体への負担が少ない手術となっています。
そのため、術後には早期の社会復帰も期待できるのです。
2020年に、パーキンソン病でのFUS治療に対して、保険が適用されるようになりました(症状など一定の条件があります)。
全身のコンディションを整えるストレスフリー療法

「ストレスフリー療法」とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30~60分照射する温熱療法。
これにより、全身の血流や自律神経を整え、高血圧や糖尿病、認知症、不眠症、冷え症、白内障など、さまざまな病気の予防・改善効果が期待できるのです。
また、ストレスフリー療法により、パーキンソン病の症状が大きく改善した実例が報告されています。
その理由として考えられるのは、「成長ホルモンの分泌亢進」と、新発見の体表点への熱刺激による「脳への大幅な血流増加」により、中脳の黒質が修復再生し、ドパミンの分泌が増えたことです。
実例を知ることで実際の診療のイメージも掴めると思いますので、気になる方は下記の診療実績ページよりご確認ください。
「銀座数寄屋橋クリニック」はストレスフリー療法に特化した治療を提供しています。
公式サイトにて、詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ

今回は、パーキンソン病の代表的な運動症状である振戦について網羅的に解説しました。
振戦は、脳の神経伝達物質ドパミンの不足により引き起こされます。
パーキンソン病以外の振戦との見分け方は、「安静時に現れるか」「筋固縮や無動など他の症状も見られるか」などに当てはまれば、パーキンソン病の振戦の可能性が高いです。
振戦により、日常生活への影響だけでなく心理的影響などもあります。
振戦に対する治療には、「抗コリン薬」や「FUS」が用いられる場合も。
さらにパーキンソン病の症状を改善する効果が期待できる「ストレスフリー療法」という選択肢もあります。
この記事が、パーキンソン病の振戦についての理解の一助になれば幸いです。






