この記事では、パーキンソン病ではなかった場合にどのような病気が考えられるのか、そしてパーキンソン病を鑑別診断する方法などを解説します。
パーキンソン病では、早期に発見して治療を開始することが重要です。
一方で、診断に際してパーキンソン病と似た他の病気と見分けることは、専門家でも難しいことも。
パーキンソン病に似た病気(パーキンソン症候群)について知りたい方、現在何らかの症状があって不安な方に、おすすめの内容です。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン病とは一体どんな病気なのか

「パーキンソン病」とは、振戦(手足の震え)や筋固縮(筋肉のこわばり)、無動(動きが遅い)、姿勢反射障害(転びやすい)などの症状が現れる神経変性疾患。
多くは50歳以上で発症しますが、40歳以下で起こることもあり、「若年性パーキンソン病」と呼ばれます。高齢になるほど発症率が高く、65歳以上では100人に1人程度です。
この病気は、脳の神経伝達物質ドパミンを産生する神経細胞が減少することで発症します。
ドパミンは主に運動の調節を司るため、その不足は身体のさまざまな運動障害を引き起こすのです。
パーキンソン病ではなかった場合に一体どのような病気が考えられるか
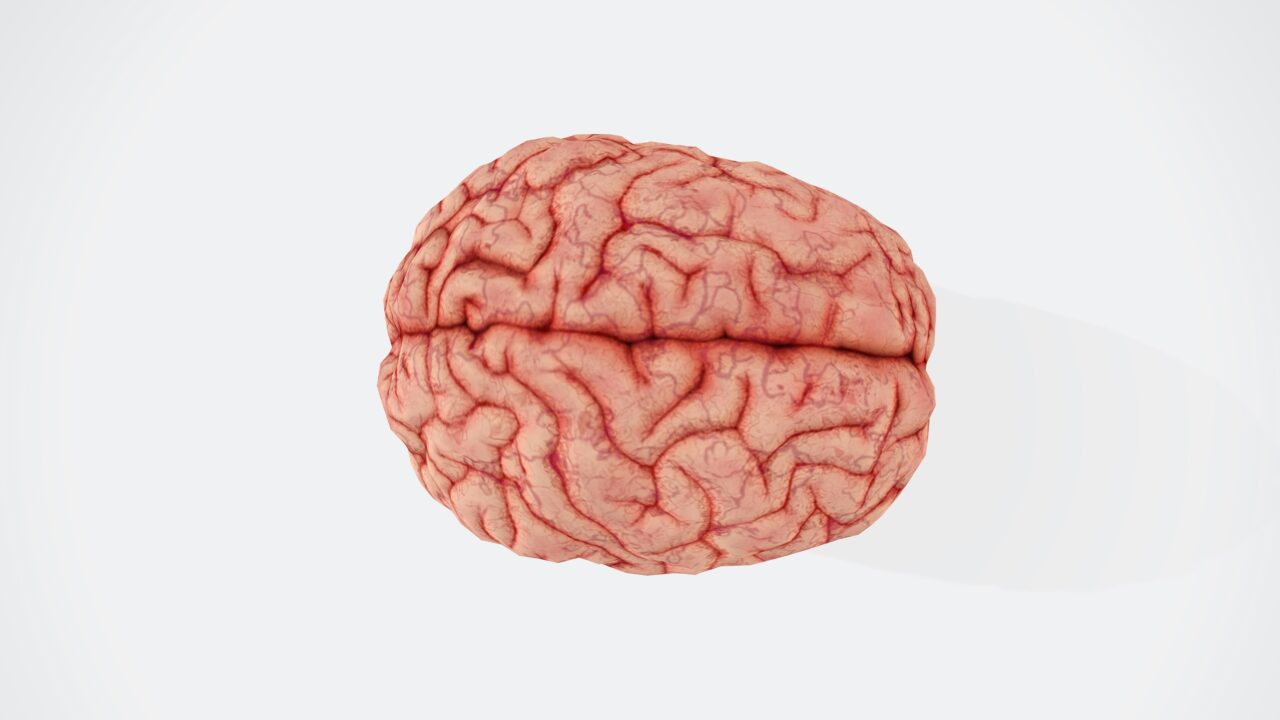
ここでは、パーキンソン病ではなかった場合にどのような病気の可能性があるかを紹介します。
パーキンソン病と似た症状をきたすさまざまな病気は「パーキンソン症候群」と総称され、パーキンソン病と区別することが困難な病気も多いです。
パーキンソン症候群は、一般的に「進行がはやい」「症状が左右対称」「パーキンソン病治療薬の効きが悪い」などの特徴があります。
レビー小体型認知症
「レビー小体型認知症」とは、大脳皮質などに「レビー小体」という異常なタンパク質が蓄積することで引き起こされる神経変性疾患です。
レビー小体は、パーキンソン病を引き起こすタンパク質でもあり、レビー小体型認知症とパーキンソン病を合わせて「レビー小体病」と呼ばれます。
レビー小体型認知症では、調子の良い時と悪い時が波のように現れながら、少しずつ症状が悪化するのが特徴。
主な症状は、以下のとおりです。
- 認知機能障害(もの忘れなどの記憶障害は比較的少ない)
- パーキンソン症状(振戦・無動・筋固縮・姿勢反射障害など)
- 幻視・幻聴
- 睡眠障害(レム睡眠行動異常など)
- 自律神経症状(便秘・起立性低血圧など)
正常圧水頭症
「正常圧水頭症」とは、脳の髄液が増加し脳室が拡大しているにもかかわらず、髄液圧が正常である疾患です。
脳や脊髄は120~150mL程度の髄液に囲まれて保護された状態に。
髄液は主に脳室で1日約500mL作られ同じ量が吸収されるので、1日3~4回入れかわることになります。
水頭症とはこの髄液の産生と吸収のアンバランスにより量が増え、脳室が異常に拡大した状態です。
正常圧水頭症の主な症状は、「歩行障害」「認知機能低下」「尿失禁」が挙げられます。
診断では、MRI検査により、「DESH」と呼ばれる特徴的な脳内の変化を示す所見があるか確認。
また、腰椎穿刺で髄液を排出し、症状が改善するかどうか確認します(タップテスト)。
多系統萎縮症
「多系統萎縮症」とは、脳や脊髄の一部が萎縮したり状態が変化したりすることで、体を動かしにくくなる神経変性疾患です。
近年、別々の疾患とされてきた3つの疾患が多系統萎縮症に統一されました。
現在では、大きく2つの病型に分けられます。共通の特徴は自律神経障害(起立性低血圧や排尿障害、便秘など)が起こることです。
「小脳型(MSA-C)」の症状は、ふらつきや協調運動の障害が最初に現れ、歩行困難、姿勢不安定、眼球運動障害、言語障害など。
「パーキンソン型(MSA-P)」の症状は、振戦や無動、筋固縮、姿勢反射障害などが挙げられます。
MRI検査で、小脳・橋・線条体の萎縮や特徴的な画像所見(「十字サイン」など)が見られると、パーキンソン病との鑑別につながります。
進行性核上性麻痺
「進行性核上性麻痺」とは、大脳基底核や脳幹、小脳などに進行性の変性が生じ、神経細胞が萎縮していく神経変性疾患です。
異常なタウタンパク質の蓄積がみられます。
症状は左右の差が小さく、初期から強い姿勢反射障害がみられ、歩行障害や上下の眼球運動障害、体幹・項部のジストニア(筋肉の緊張異常により後ろに反り返る)などです。
また、構音障害や嚥下障害、認知機能の低下がみられることも。
MRI検査では、中脳被蓋が萎縮してハチドリの形に見えるハミングバード徴候や、第三脳室の拡大がみられます。
大脳皮質基底核変性症
「大脳皮質基底核変性症」とは、大脳基底核および大脳皮質の神経細胞が脱落し、パーキンソン症状と大脳皮質症状がみられる神経変性疾患です。
異常なタウタンパク質の蓄積がみられます。
パーキンソン症状は、左右非対称の筋固縮や無動、ミオクローヌス(素早いぴくつき)、ジストニア(姿勢異常)などです。
大脳皮質症状には、以下のものがあります。
- 肢節運動失行(動作がぎごちない)
- 構成失行(空間的把握が困難)
- 高次脳機能障害(失語、半空間無視など)
- 他人の手徴候(手が意思に反して動く)
- 把握反射
- 認知機能障害
MRI検査では、初期には異常は見られませんが、進行とともに左右非対称の大脳萎縮(前頭葉、頭頂葉)が認められます。
薬剤性パーキンソン症候群
「薬剤性パーキンソン症候群」とは、薬剤の副作用が原因となるパーキンソン症候群。
原因となる薬剤は、ドパミン受容体をブロックする作用をもつものになります。例えば、一部の抗精神病薬や胃腸薬です。
症状は左右対称に出現し、パーキンソン病でみられる症状以外に、動作時振戦、口舌ジスキネジア(口や舌が勝手に動く)、アカシジア(じっとしていられない)などがみられることもあります。
薬剤性パーキンソン症候群の治療では、原因となる薬剤の段階的な減量や中止を基本とし、必要に応じてパーキンソン病治療薬を併用。
診断では、問診と診察が基本です。服薬歴の確認や各種検査データ(DATスキャンなど)を組み合わせながら、判断を進めます。
脳血管性パーキンソン症候群
「脳血管性パーキンソン症候群」とは、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害が原因となるパーキンソン症候群です。
特に、脳の深部にある基底核や、大脳皮質の下にある白質と呼ばれる部分が損傷を受けると、パーキンソン症状が出やすくなります。
症状は、歩行障害や姿勢の不安定さが目立ち、振戦はパーキンソン病ほど強くないことが多いです。
MRI検査で脳の奥深くに小さな梗塞が多数見られる場合は、脳血管性パーキンソン症候群の可能性も。
パーキンソン病を見分ける方法

パーキンソン病は、他の病気との判別が難しいとされます。
診断は問診と診察を中心に行いますが、診断をより確実なものにするために行うのが画像検査や嗅覚検査です。
さらに、診断を確定するために、薬の効き具合を試す場合も。
以下、パーキンソン病を見分けるための検査の方法を解説します。
脳血流スペクト検査
「脳血流スペクト検査」とは、放射性同位体で標識された薬剤を注射し、脳の血流分布を画像化する検査です。
認知機能障害を伴うパーキンソン病の場合には、レビー小体型認知症と同様に後頭葉皮質を中心とした血流低下が認められます。
この所見は、後部帯状回や楔前部の血流が低下するアルツハイマー病とは異なることから、鑑別上有用と考えられています。
また、正常圧水頭症や多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症などでも、それぞれ脳の特定部位での血流変化が見られ、それらの診断にも有用な検査。
MRI脳画像検査
「MRI(核磁気共鳴画像法)」とは、核磁気共鳴現象を利用して脳の断層写真を撮影する検査です。
放射線被曝のリスクはありません。
この検査では、脳を解剖学的に評価し、通常と比べて形の変化がないかを観察します。
パーキンソン病の場合、MRI脳画像検査では「特異的な異常がない」のが特徴です。
パーキンソン症候群では、正常圧水頭症や多系統萎縮症など、特徴的な画像所見がみられることが多く、それらの病気との鑑別のために有用とされます。
MIBG心筋シンチグラフィ
「MIBG心筋シンチグラフィ」とは、心臓の交感神経の働きを画像化する検査です。
これは、MIBG(メタヨードベンジルグアニジン)というノルアドレナリンに似た構造で同様の挙動を示す放射性医薬品を注射し、この薬剤の心臓への集積の程度を評価するという検査方法になります。
パーキンソン病やレビー小体型認知症では心臓への取り込みが低下します。
しかし、この低下は他のパーキンソン症候群では一般的に認められないため、鑑別診断に有用です。
ドパミントランスポーターシンチグラフィ
「ドパミントランスポーターシンチグラフィ(DATスキャン)」とは、脳の黒質から線条体に向かうドパミン神経に存在するドパミントランスポーターを画像化する検査です。
この検査を行うことで、ドパミン神経の変性・脱落の程度を評価できます。
なお、この検査では放射性標識された薬剤の静脈注射が必要。
パーキンソン病やレビー小体型認知症、多系統萎縮症、進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症では、ドパミントランスポーターの密度の低下が見られます。
大脳皮質基底核変性症では、左右差が出るのが特徴です。
嗅覚検査
「嗅覚検査」とは、患者にさまざまなにおいを嗅がせて識別できるかを評価するもので、非侵襲的な検査です。
なお、パーキンソン病では、運動症状が現れるよりも早い段階から「嗅覚障害」が高頻度でみられます。
国内で使用される検査方法は主に3種類。
そのうちの1つで日本人向けに開発された「OSIT-J」は、12種類のにおい(香水・バラなど)の中から特定のにおいを識別する能力を評価します。
この検査でのパーキンソン病患者の平均正答率は、12問中4.5問程度です。
他のパーキンソン症候群の患者と比べて有意に低いという報告があります。
全身のコンディションをサポートするストレスフリー療法

「ストレスフリー療法」とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30~60分照射する温熱療法。
これにより、全身の血流や自律神経を整え、高血圧や糖尿病、認知症、不眠症、冷え症、白内障など、さまざまな病気の予防・改善効果が期待できるのです。
また、ストレスフリー療法により、パーキンソン病の症状が大きく改善した実例が報告されています。
その理由として考えられるのは、「成長ホルモンの分泌亢進」と、新発見の体表点への熱刺激による「脳への大幅な血流増加」により、中脳の黒質が修復再生し、ドパミンの分泌が増えたことです。
「銀座数寄屋橋クリニック」はストレスフリー療法に特化した治療を提供しています。
公式サイトにて、詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ
今回は、パーキンソン病ではなかった場合に、どのような病気の可能性があるかなどを解説しました。
パーキンソン病と似た症状がみられる病気(パーキンソン症候群)には、以下のようなものがあります。
①神経変性疾患:「レビー小体型認知症」「多系統萎縮症」「進行性核上性麻痺」「大脳皮質基底核変性症」
②神経変性疾患以外:「正常圧水頭症」「薬剤性パーキンソン症候群」「脳血管性パーキンソン症候群」
パーキンソン病とこれらの病気との区別は難しく、問診や診察に加え、画像検査や嗅覚検査などを行い診断に役立てます。
薬やリハビリ以外に「ストレスフリー療法」などの選択肢もあるので、ぜひ参考にしてください。






