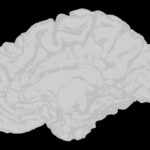パーキンソン病は加齢に伴い発症率が増加することで有名な難病。
そのため、高齢者だけの病気と思われがちですが、実は働き盛りの40代からでも発症することがある病気なのです。
パーキンソン病について気になる方に向けて、本記事では、治療薬の基本情報・効果・副作用について詳しく解説します。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン病とは

パーキンソン病は、運動機能や自律神経に影響を与える進行性の神経変性疾患です。
この病気の主な症状は手足の震え(振戦)、動作が遅くなる(無動・寡動)、筋肉のこわばり(筋強剛)などであり、最終的には転びやすくなるなどの姿勢反射障害が見られます。
主な原因は、脳内で運動指令を調整する物質「ドパミン」の減少です。
特に50歳以上で発症することが多いですが、40歳以下でも「若年性パーキンソン病」として発症することがあります。
パーキンソン病薬一覧

パーキンソン病の治療には、症状の進行を遅らせたり緩和するための薬物療法が治療の中心。
パーキンソン病の薬物療法には、様々な薬が用いられます。
ここからは、パーキンソン病の治療に用いられる薬について解説していきます。
Lドパ製剤
Lドパ製剤は、パーキンソン病治療における重要な薬で、脳内で欠乏しているドパミンを補充する作用があります。
Lドパは血液脳関門を通過し、ドパミンに変化することで症状を改善。
ただし、Lドパが脳内に到達する前に分解されることを防ぐため、分解されにくくする物質などを組み合わせた製剤が多く使用されています。
また、治療効果の持続時間が短くなる「ウェアリングオフ現象」への対応として、Lドパを代謝するCOMTという酵素の働きを阻害するCOMT阻害薬の併用が有効です。
Lドパ製剤の副作用には吐き気、不随意運動、消化器症状などがあり、慎重な服用が求められます。
抗コリン薬
パーキンソン病の治療で使用される抗コリン薬は、脳内のアセチルコリンという神経から神経や筋肉へ情報を伝える「神経伝達物質」の働きを抑え、症状を緩和します。
パーキンソン病ではドパミンが不足し、アセチルコリンとのバランスが崩れるため、手の震え(振戦)などの症状が出やすくなります。この薬は、特に振戦の改善に効果的です。
高齢者の場合、副作用として認知機能の低下や便秘、口渇、視力障害などが現れることがあるため、慎重な使用が求められます。
主に早期の段階や症状が特定のケースで使用されることが多いといわれています。
COMT阻害薬
COMT阻害薬は、パーキンソン病治療の一環として重要な役割を果たす薬剤。
この薬は、「カテコール-O-メチル基転移酵素(COMT)」と呼ばれる酵素を阻害します。
COMTは治療薬「Lドパ」を代謝してしまうため、Lドパの脳内への移行を妨げることがあります。
この薬を使用することで、Lドパの効果が持続しやすくなり、ドパミンの脳内濃度を維持する助けとなるのです。
結果、パーキンソン病の症状である振戦(手の震え)や筋肉のこわばりが改善され、ウェアリングオフ現象(薬効の時間が短くなる問題)も軽減することが期待できます。
副作用として、ジスキネジー(不随意運動)や消化器症状、幻覚などが報告されるため、医師の監視が重要。
レボドパとの併用が基本となるため、単独では効果を発揮しないことにも留意しなければなりません。
MAO-B阻害薬
MAO-B阻害薬はモノアミン酸化酵素B(MAO-B)を阻害し、ドパミンの分解を防ぐことで、脳内のドパミン濃度を高めます。
主にパーキンソン病の治療に用いられ、症状を改善し、レボドパの効果を補完。
セレギリン、ラサギリン、サフィナミドという薬が一般的な薬で、それぞれ特徴が異なります。
ただし、副作用として血圧低下や不眠などが現れることがあるため、慎重な監視が必要です。
詳細な効果と注意点を確認しながら使用することが推奨されます。
ドパミンアゴニスト製剤
ドパミンアゴニスト製剤は、脳内のドパミン受容体を直接刺激し、ドパミンに似た働きをする薬です。
主にパーキンソン病の治療で使用され、運動症状の改善に役立ちます。
麦角系(心臓弁膜症のリスクあり)と非麦角系(突発的睡眠の副作用あり)に分類。
患者の年齢や症状に応じて使い分けられます。
非麦角系は第一選択薬とされる場合が多く、レボドパ製剤との併用で効果を高めることが期待されています。
副作用には、突発性睡眠、悪心、嘔吐、精神症状(幻覚・せん妄)があり、患者ごとのリスク管理が重要です。
特に高齢者では精神症状や認知障害のリスクが高いため、慎重な使用が推奨されます。
ゾニサミド
ゾニサミドは、てんかんとパーキンソン病治療に用いられる薬です。
その作用機序として、電位依存性ナトリウムイオンチャネルおよびカルシウムチャネルの抑制、炭酸脱水酵素阻害が挙げられます。
てんかんでは過剰な神経興奮を抑え発作を減少させ、パーキンソン病ではドパミン神経伝達を調整し運動症状を改善します。
特に、レボドパ製剤の効果を補助し、ウェアリングオフ現象に対応。
ただし、副作用には眠気、食欲不振、体重減少があり、慎重な使用が求められます。
アマンタジン
アマンタジンは、ドパミン放出促進作用とNMDA受容体拮抗作用を持つ薬です。
パーキンソン病や薬剤性パーキンソニズムの治療に用いられます。
また、動作緩慢や振戦などの運動症状を改善し、進行期でのレボドパ誘発性ジスキネジアに効果を示すことがあります。
レポドパ誘発性ジスキネジアとは、パーキンソン病治療薬レボドパを長期間使用することで生じる副作用。
手足や顔などに意図しない不随意運動が現れることが多いです。
アマンタジンの副作用には、不眠、口渇、幻覚、便秘、めまいなどが挙げられ、特に高齢者や腎機能障害のある患者では慎重な使用が求められます。
パーキンソン病の治療においては、他の薬との併用が一般的です。
アデノシンA2A受容体拮抗薬
アデノシンA2A受容体拮抗薬は、パーキンソン病治療薬として使用。
脳内のアデノシンA2A受容体を阻害し、運動機能を低下させるGABAの過剰分泌を抑えます。
アデノシンA2Aとは、脳などに存在するプリン受容体の一種で、細胞の機能を調節し、ドーパミンの作用を補助する役割を持っています。
この薬はウェアリングオフ現象の改善に効果的で、レボドパ製剤との併用療法が一般的です。
副作用には眠気、幻覚、便秘などがあるため、慎重な使用が推奨されます。
ドロキシドパ
ドロキシドパは、パーキンソン病や起立性低血圧の治療に用いられる医薬品です。
体内でノルアドレナリンに変換されるプロドラッグとして作用し、血圧低下や運動機能の改善に寄与します。
ノルアドレナリンとは、交感神経が活性化した際に分泌されるホルモン。
脳内では、神経伝達物質としての役割も担っています。
ストレスを受けたときなど、心拍数の増加や血圧の上昇、集中力の向上を促します。
プロドラックとは、一旦体内に入ると酵素などの働きで薬効を持つ化合物に変換される薬のことです。
ドロキシドパは、レボドパでは改善が難しい「すくみ足」や立ちくらみなどに効果が期待されています。
副作用には、頭痛や幻覚、便秘などが含まれる場合があるため、慎重な服用が必要です。
全身のコンディションをサポートするストレスフリー療法

ストレスフリー療法は、パーキンソン病の治療において効果が期待される新しいアプローチです。
この療法は、「ストレスフリー療法」とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30分~60分照射する温熱療法。
ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させることで血流を増加させ、神経や身体の機能を改善します。
結果として、患者は認知機能や情緒的な安定感が向上し、運動機能にも良い影響を与える可能性があります。
「銀座数寄屋橋クリニック」はストレスフリー療法に特化した治療を提供しています。
公式サイトにて、詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ

パーキンソン病の治療薬には、さまざまな薬が用いられます。
1人1人に合わせた治療法により、生活の質を向上させることがパーキンソン病を治療する際のポイント。
薬の副作用にも注意する必要があります。
ストレスフリー療法も全身のコンディションをサポートする方法の一つです。
パーキンソン病について分からないことがある場合、主治医に相談しましょう。