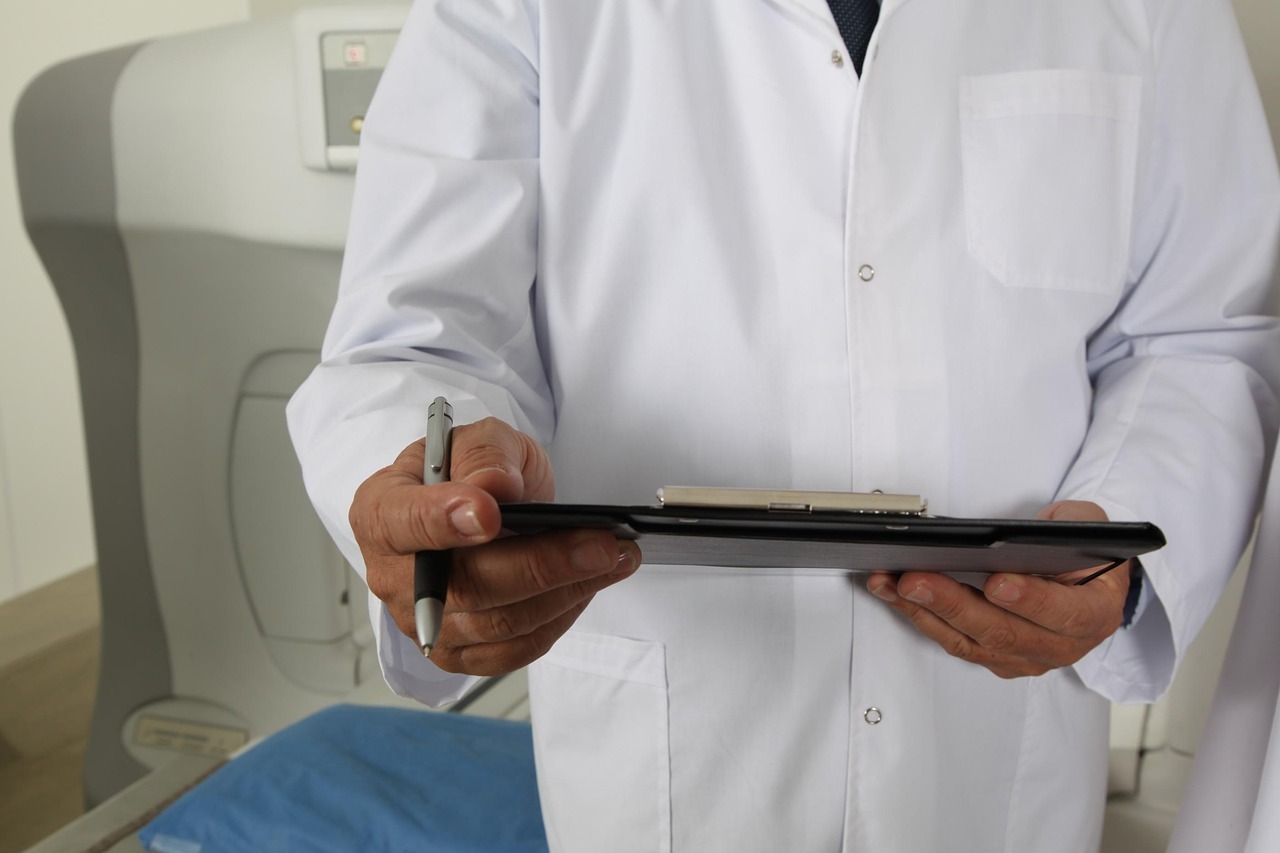パーキンソン病とレビー小体型認知症、どちらも40代以降の人生に影響を及ぼす可能性がある疾患ですが、その違いをご存じですか。
年齢を重ねるにつれて、これらの病気について関心が高まっている方や、自分の家族が高齢になり、病気や治療、介護について考える機会が増えて、知識を蓄えて置きたい方などに向けて、運動機能障害から認知症状まで、多岐にわたる両疾患の特徴を分かりやすく解説します。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

レビー小体型認知症とは一体どんな病気なのか
レビー小体型認知症は、認知機能の低下や幻視、運動症状などを特徴とする進行性の疾患です。
この病気は脳内にレビー小体と呼ばれる異常なタンパク質が蓄積することで発症します。
症状としては、記憶力の低下や混乱、空間認識の障害などが見られるほか、幻視やパーキンソン病に類似した運動症状も含まれる場合があります。
レビー小体型認知症はアルツハイマー病やパーキンソン病と似た部分を持ちながらも、独自の特徴を備えています。正確な診断と適切な治療を早期に受けることが、症状の進行を緩和し、患者さんの生活の質を向上させるために重要とされています。
社会的な支援も含めた包括的なケアが求められます。
パーキンソン病とは一体どんな病気なのか
パーキンソン病は、神経変性疾患の一つで、特に運動機能に影響を及ぼします。
この病気は、脳内のドーパミンを生成する神経細胞が徐々に失われることで発生します。
主な症状としては、手足の震え(振戦)、筋肉の硬直、動きの遅さ(寡動)、姿勢の不安定さなどが挙げられます。
また、進行につれて認知機能の低下やうつ症状が見られることもあります。
治療には、薬物療法やリハビリテーションが中心であり、症状を管理し生活の質を向上させることが目標です。
早期診断と適切な治療の組み合わせが、患者さんの能力を最大限に引き出す鍵となります。
社会的な支援を含めた包括的なケアも重要です。
レビー小体型認知症とパーキンソン病を鑑別する際のポイント
レビー小体型認知症とパーキンソン病は、どちらも脳に影響を及ぼした結果、認知機能の低下や運動機能に影響を及ぼす病気という共通点があります。
では、この2つの病気を鑑別するにはどういったポイントに注目すればよいのでしょうか。
問診
レビー小体型認知症とパーキンソン病の問診による鑑別では、初期症状に焦点を当てます。
レビー小体型認知症は認知機能の変動、幻視、レム睡眠行動異常症などが特徴で、これらの症状が早期から現れることがあります。
一方、パーキンソン病は運動症状(振戦、筋硬直、寡動)が先行し、認知機能低下は進行とともに現れることが多いです。
また、生活史や睡眠の質、精神症状を詳しく聞くことで鑑別に役立ちます。
どちらも、早期診断が治療方針を左右するため、症状の詳細な評価が重要です。
認知機能検査
認知機能検査を用いた鑑別では、レビー小体型認知症とパーキンソン病の特徴的な違いに焦点を当てます。
まず、レビー小体型認知症では注意や認知機能が一時的に改善する「認知機能の変動」が見られる場合があります。
また、幻視や実行機能の低下が早期に現れることが多いのも特徴です。
一方、パーキンソン病では運動機能に関連する症状が先行し、認知機能の低下が進行後に発症することが一般的です。
検査では、注意力や記憶力、問題解決能力を測定するテスト(例:MMSEやMoCA)が役立ちます。
レビー小体型認知症の可能性がある場合、視空間認知や幻視に特化した項目がより重点的に評価されます。
一貫したテスト結果と臨床症状を組み合わせることで、疾患の鑑別がより正確に行えます。
血液検査
血液検査によるレビー小体型認知症とパーキンソン病の鑑別では、特定のバイオマーカーの検出が注目されています。
たとえば、レビー小体型認知症では「α-シヌクレイン」というタンパク質が異常に蓄積するため、これを血液中で検出する技術が研究されています。
さらに、「ニューロフィラメント軽鎖」などの神経変性マーカーも役立ちます。
一方で、パーキンソン病でも同様のマーカーが現れることが多く、これらを量的や質的に比較することで診断の手がかりとなります。
診断の精度向上には、血液検査に加え、臨床症状や他の検査結果との総合的な評価が必要です。
脳の画像検査
レビー小体型認知症とパーキンソン病の鑑別には、主に以下の画像検査方法を使います。
それぞれ異なる特徴を持ち、補完的な役割を果たします。
ダットスキャン(DaTスキャン)
・レビー小体型認知症では、ドーパミントランスポーターの減少が広範囲に起きるため、線条体の集積低下が画像で確認できます
・一方、パーキンソン病でも線条体の変性が顕著ですが、運動障害との関連で変化が観察されます
脳血流SPECT検査
・レビー小体型認知症は後頭葉血流の著しい低下を特徴とし、視覚的幻覚との関連が指摘されています
・対して、パーキンソン病は黒質や線条体の血流異常が中心となります
MIBG心筋シンチグラフィ
・レビー小体型認知症では、心臓交感神経障害が顕著で、心縦隔比の低下が画像で確認できます
・パーキンソン病でも同様の所見が見られる場合が多いですが、レビー小体型認知症ほど顕著でない場合もあります
123I-MIBG心筋シンチグラフィ
123I-MIBG心筋シンチグラフィとは、心臓交感神経の機能を評価する検査です。
放射性医薬品123I-MIBGを注射し、心臓への取り込みを画像化します。
この取り込みは、心不全や自律神経の異常を反映し、パーキンソン病やレビー小体型認知症の鑑別にも活用されます。
検査は15分後と数時間後の2回行い、心縦隔比(H/M比)から交感神経障害の程度を評価します。
これにより、疾患の進行度や治療方針の判断が可能です。
睡眠検査
レビー小体型認知症とパーキンソン病を区別するためには、睡眠検査も重要な鑑別方法のひとつです。
特にレム睡眠行動障害の有無がポイントとなると言われており、レビー小体型認知症では、夢の内容を実際の動作に表す症状が多く見られ、睡眠ポリグラフ検査で動作の異常が確認されることがあります。
一方で、パーキンソン病でも同様の症状が出る場合がありますが、頻度や程度が異なることが特徴で、この検査結果を他の症状と合わせて鑑別します。
全身のコンディションを整えるストレスフリー療法

ストレスフリー療法は、パーキンソン病の治療において効果が期待される新しいアプローチです。
ストレスフリー療法とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30分~60分照射する温熱療法です。
ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させることで血流を増加させ、神経や身体の機能を改善します。結果として、患者は認知機能や情緒的な安定感が向上し、運動機能にも良い影響を与える可能性があります。
当療法に特化した専門クリニックとして信頼されているのが、「銀座数寄屋橋クリニック」です。
公式サイトや診療実績ページにてさらに詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ
レビー小体型認知症もパーキンソン病も脳に異常が生じ、認知機能や運動機能に影響を与える病気で、加齢に伴い発症率が上がる疾病です。
レビー小体型認知症とパーキンソン病を鑑別するには、問診をはじめとする、運動機能検査、血液検査、画像診断、睡眠検査などにより、
症状や状態を見比べることで鑑別していきます。
どちらも薬物療法や運動療法を組み合わせることで、症状の改善や進行の緩和などができるとされており、たとえ、レビー小体型認知症やパーキンソン病になったとしても、今の生活を諦めることなく、早期診断と早期治療で、いつまでも自分らしい生活を送りましょう。