「最近なんとなく動きづらい」「手が震える」など、40代から始まる体の変化に、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
将来に備えて知っておきたい病気のひとつが、パーキンソン病です。
そこで今回は、パーキンソン病を詳しく説明し、主な症状や原因を併せて紹介します。
体の小さなサインを見逃さず、日々の健康を守りましょう。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン病とは一体どんな病気なのか
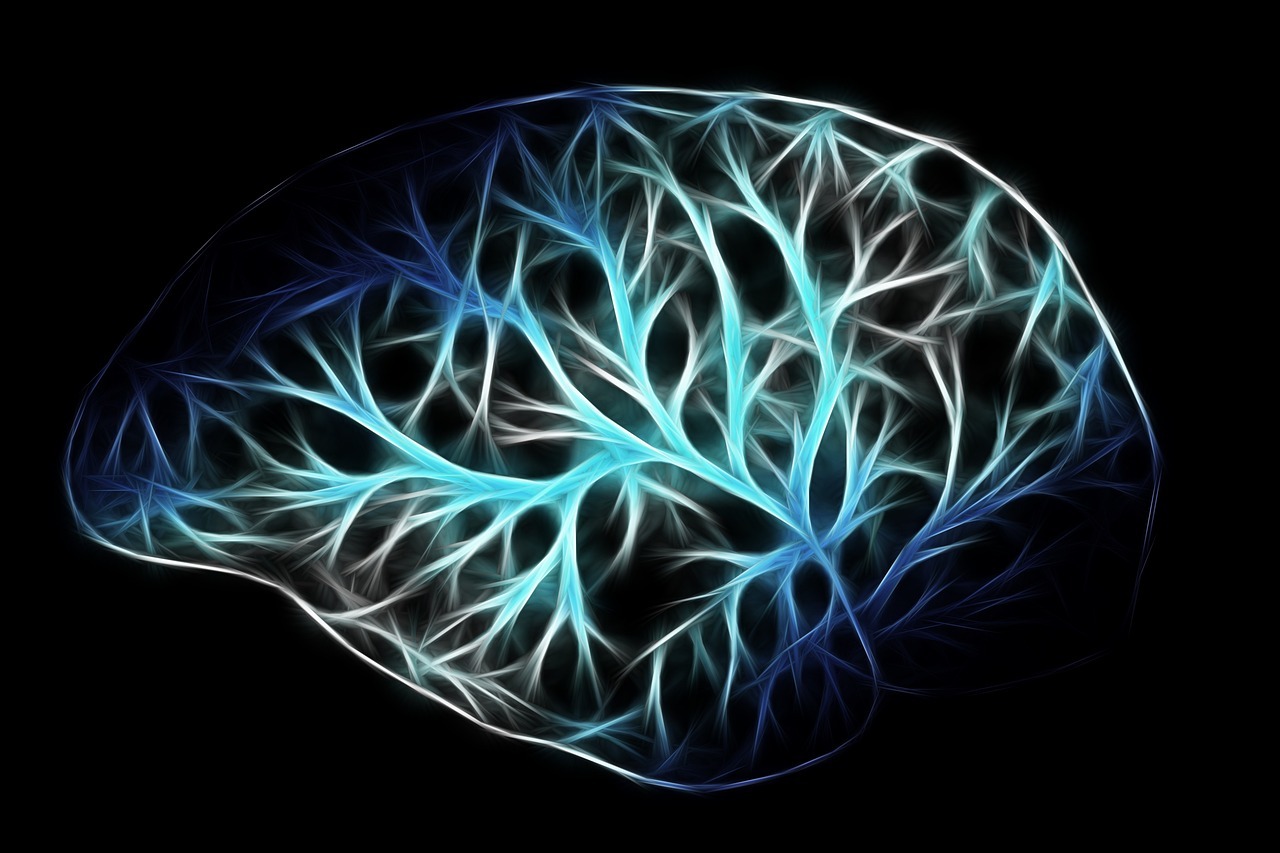
パーキンソン病とは、手足の震えや動作が遅くなる・筋肉がこわばる・転びやすくなるなど運動の症状があらわれる病気です。
脳内の神経伝達に関わるドパミンという物質が減ることで発症。
50歳以降に多く見られますが、40歳以下で発症する若年性パーキンソン病もあります。
徐々に進行するため、治療やリハビリで症状を和らげながら日常生活を続けていくことが可能です。
パーキンソン病の主な原因とは

パーキンソン病は、中脳の黒質と呼ばれる場所のドパミン神経細胞が減少することで起こると考えられています。
ドパミンは、体の動きをスムーズに保つために必要な神経伝達物質。
不足すると体の動きが鈍くなったり、震えが出たりします。
主な原因は、まだ解明されていません。
最近では、アルファ-シヌクレインというタンパク質の蓄積が、ドパミン神経の減少に関係していると考えられています。
一部には遺伝的な要因も関与していますが、適切な治療により症状をコントロールし日常生活を維持することが可能です。
パーキンソン病の主な症状とは

パーキンソン病とは、主に振戦(ふるえ)・動作緩慢・筋強剛(筋肉のこわばり)・姿勢保持障害(転びやすさ)などの運動症状が現れる病気です。
さらに、便秘や疲れやすさなど日常生活に関わる症状もみられることがあります。
そこで、6つの代表的な症状について詳しく紹介します。
振戦
パーキンソン病の代表的な症状のひとつに振戦(しんせん)があります。
症状は体の一部が震えること。
特に手がじっとしているときに細かく震える点が特徴です。
例えば、椅子に座って手を上に置いているとき、歩いているときなど力を抜いている場面であらわれやすくなります。
これは静止時振戦(せいしじしんせん)。
物を持ったり、体を動かすと震えが軽くなることもあります。
多くの方が、日常生活に不安を感じる症状です。
この振戦は、パーキンソン病を公表した有名人にも見られました。
俳優のマイケル・J・フォックス氏は、手の震えを初期症状として経験しています。
振戦は、パーキンソン病の早期の気付きの手がかりになる大切な症状です。
動作緩慢
動作緩慢(どうさかんまん)は、パーキンソン病にみられる特徴的な運動症状のひとつです。
医学的には寡動(かどう)や無動(むどう)とも呼ばれ、体を動かすスピードが緩やかになったり、動きだしが遅くなる点が特徴です。
初期症状として現れることもあり、歩こうとしても足が前に出にくい(すくみ足)や声が小さくなる、字が小さくなる症状も。
日常動作に、さまざまな影響を与えます。
脳の神経細胞が減少し、動きをコントロールする機能がうまく働かなくなる病気です。
どれかひとつでもあてはまる症状があれば、早めに専門医に相談されることをおすすめします。
筋固縮
パーキンソン病の運動症状のひとつに筋固縮(筋強剛)は肩や膝、指の筋肉が固くなり、動かしにくくなる症状です。
動作がスムーズにいかず、日常生活で疲れやすさや痛みを感じることもあります。
また、顔のこわばりや表情が乏しくなるのも特徴。
これらの症状は、本人が気付きにくい場合もあります。
なので大切なのは、周囲の方や専門医が早期に気付くことです。
筋固縮は、パーキンソン病の診断で重要なポイントで、適切な治療やリハビリで症状の緩和を目指せます。
あきらめずに対処していきましょう。
姿勢保持障害
姿勢保持障害(しせいほじしょうがい)は、パーキンソン病でよくみられる症状のひとつです。
体のバランスを保つのが難しくなり、転びやすくなるのが特徴で、歩いている途中で止まることができなくなる症状が現れます。
方向を変えるときのつまずき・症状の進行により、首が下がったり、体が傾いてしまうことも。
転倒による骨折のリスクも高まります。
病気が進行してから転びやすくなるため、注意が必要です。
転倒を防ぐためにも、適切なリハビリを心がけましょう。
便秘
パーキンソン病の初期症状のひとつに便秘があります。
自律神経の働きが弱まり、腸の動きが鈍くなるのが原因と考えられています。
治療薬の副作用で便秘が起こることもあり、症状が辛くなることも。
実は、便秘だけが先に出ていたという方も少なくないです。
長く続く便秘がある場合は、パーキンソン病の初期症状がどうか見極めましょう。
易疲労性
易疲労性とは、少しの動作、活動で疲れやすくかんじる状態です。
体の動きが遅くなるだけでなく、少しの動作でも疲労感が強くなることがあります。
病気による筋肉のこわばりやエネルギーの使い方の変化が、影響しているのかもしれません。
疲れやすいと感じたら無理せず休むことが大切ですが、症状が続く場合は専門医に相談してみましょう。
パーキンソン病の早期発見にもつながります。
パーキンソン病の治療法
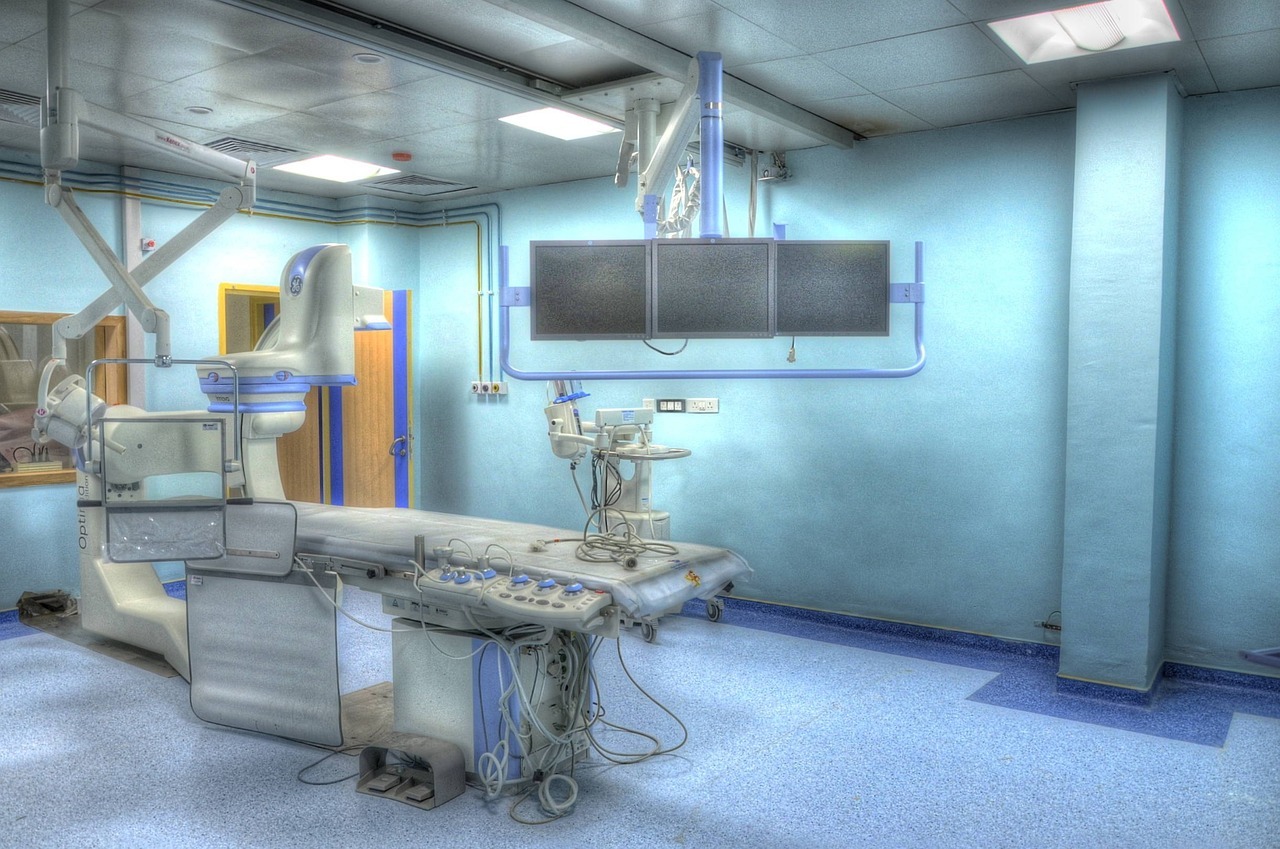
パーキンソン病の治療には、症状を和らげて日常生活をサポートする3つの方法があります。
そこで、薬による治療や手術に加え、心と体の負担を軽くするストレスフリー療法を詳しく紹介していきます。
それぞれの特徴を解説していくので、ご自身に合った方法を見つける参考になれば幸いです。
薬物治療
パーキンソン病の薬物治療は、症状や進行度に応じてL-ドパ・ドパミンアゴニストなど、複数の薬を組み合わせておこなわれます。
L-ドパは脳内で不足したドパミンを補い、運動機能の改善に役立ちます。
ドパミンの分解を防ぐ酵素阻害薬・受容体に直接働く薬を併用し、効果を高めます。
薬の形態は飲み薬の他、貼付剤や注射薬もあり、患者の状態に合わせて選択。
治療にかかる費用は、健康保険適用で、月に数千円から1万円前後が目安です。
一方で、新しい貼付剤や注射薬などを使用する場合は、やや高額になることもあります。
また、一定の条件を満たすと指定難病として医療費助成の対象になる場合も。
自己負担の軽減が期待できるため、主治医や自治体の窓口で確認しておくと不安もなくなり安心です。
手術
パーキンソン病の手術療法は、薬の効果が弱まったり副作用が強く出たりしたときに検討されます。
脳の視床下核を電気刺激で調整する脳深部刺激療法(DBS)が代表的です。
この手術により体の動きが改善し、症状のコントロールがしやすくなります。
手術費用は健康保険が適用され、自己負担は数十万円程度。
指定難病の助成が利用できる場合もあります。
手術が必要かどうか、費用についても主治医とよく相談のうえ、不安をなくしましょう。
ストレスフリー療法
ストレスフリー療法は生活習慣病や自律神経の乱れ、不眠や冷えなど、心と体のバランスを整える温熱療法です。
体にやさしく、薬に頼らない点が特徴に挙げられます。
専用の導子をツボにあて、遠赤外線を照射。
コチゾール(ストレスホルモン)の低下や血流改善、腸の働きを活性化するなど体本来の回復力を引き出します。
無理のない方法で疲れや、ストレスを和らげたい場合に適しています。
料金は通常6回コースで132,000円(税込)。
医療機関でパーキンソン病とついているの方には無料モニターの募集も行っています。
当療法に特化した専門クリニックとして信頼されているのが、「銀座数寄屋橋クリニック」です。
公式サイトにてさらに詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ

ドパミン神経の減少が主な原因のパーキンソン病は、手の震えや動作の遅れ、便秘などのさまざまな症状がみられます。
治療には薬物療法や手術が中心ですが、ストレスフリー療法の心身に優しい選択肢を生活に取り入れることも選択肢のひとつ。
無理のない方法で、自分に適した治療を見つけることが大切です。
早期発見・治療を心がけましょう。






