パーキンソン病は、脳内でドーパミンを分泌する神経細胞が減少することで発症する神経変性疾患です。
手足の震え(振戦)、筋肉のこわばり(硬直)、動作の遅れ(動作緩慢)などの運動症状が現れるほか、嗅覚障害や抑うつなどの非運動症状も特徴。
パーキンソン病の疑いやパーキンソン症候群などもあり、医師から伝えられると戸惑う方も多いでしょう。
この記事では、そんな不安を少しでも改善するためにパーキンソン病のリハビリについて解説していきます。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン病とは一体どんな病気なのか
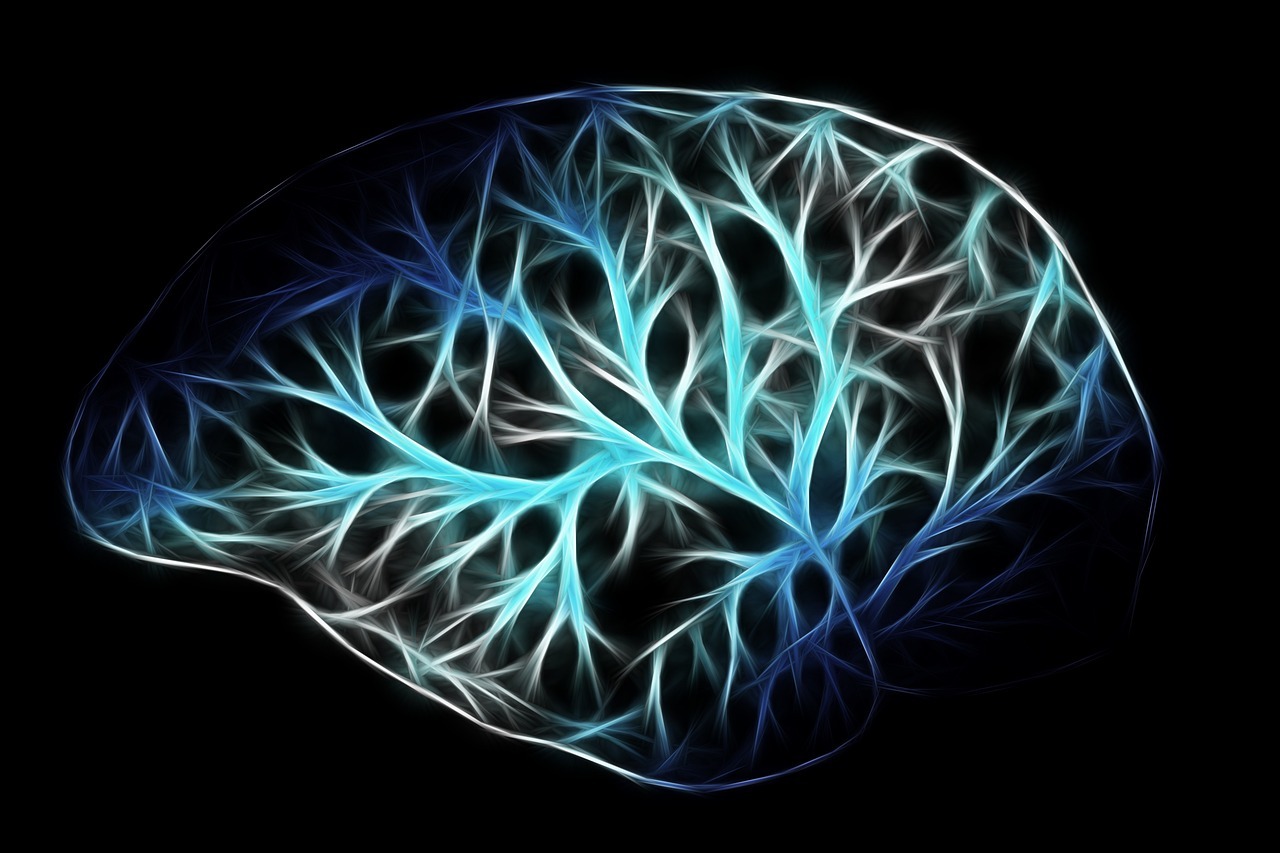
パーキンソン病は、脳内でドーパミンを生成する神経細胞の減少が主な原因となる神経変性疾患。
この病気は運動機能と非運動機能の両方に影響を与えるため、早期の診断と適切な治療が重要です。
主な症状として、以下のものが挙げられます。
- 運動症状: 手足の震え(振戦)、筋肉のこわばり(硬直)、動作の遅れ(動作緩慢)
- 非運動症状: 嗅覚障害や抑うつ、認知機能の低下
パーキンソン病の治療には、薬物療法の他に、脳深部刺激療法、再生医療などがあります。
リハビリで症状を緩和することも治療のポイントです。
パーキンソン病におけるリハビリの基本原則

パーキンソン病のリハビリには基本的な原則がいくつかあります。
どの原則もパーキンソン病の治療や症状の緩和につながる大切なものですので、しっかりと把握した上で、適切なリハリテーションを実施していきましょう。
目標設定・個別化されたリハビリ計画が重要
パーキンソン病のリハビリでは、目標設定と個別化された計画が鍵となります。
患者一人ひとりの症状や進行具合、生活環境は異なるため、それぞれに適したリハビリ計画を立てることが重要です。
例えば、日常生活の自立維持を目標とした場合、具体的な動作訓練や筋力向上のプログラムを作成。
患者自身の目標や能力に基づく計画は、モチベーションを高めるだけでなく、効果的な成果を導きやすくします。
また、定期的な評価と適応も計画の質を向上させるための重要な要素です。
個別化されたアプローチで患者の生活の質を向上させることを目指します。
専門家のサポートが重要
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のサポートは、リハビリを行う上で欠かせない存在です。
理学療法士は運動機能の改善を通じて自立した生活を支援し、作業療法士は日常動作や社会参加を促す専門家。
また言語聴覚士は、発声や嚥下機能の障害に対して治療や指導を行い、コミュニケーションや食事の質を向上させます。
この三者が連携し、患者一人ひとりに合わせた総合的なリハビリ計画を提供することで、心身の回復と生活の質の向上を目指します。
パーキンソン病におけるリハビリの方法

ここまで、パーキンソン病とは何かという基本について説明し、パーキンソン病にリハビリテーションが重要であることと、パーキンソン病のリハビリテーションの原則について解説してきました。
そしてここからは、パーキンソン病の具体的なリハビリ方法について説明していきます。
ストレッチ
パーキンソン病のリハビリでは、ストレッチが重要な役割を果たします。
筋肉の柔軟性を高めることで、固縮や姿勢の崩れを改善し、症状の進行を遅らせる効果があります。
例えば首や肩のストレッチは姿勢を整え、背中や体幹の運動はバランスを向上。
また、太ももの後ろ側を伸ばす運動は歩行の安定性に寄与します。
ストレッチは日常的な負担を減らし、関節の可動域を広げます。
筋力トレーニング
パーキンソン病のリハビリにおいて、筋力トレーニングは重要な役割を果たします。
筋肉のこわばりや筋力の低下が進行することで日常動作に支障をきたしますが、筋力トレーニングにより筋肉を強化し、関節の安定性を保つことが可能です。
また、筋肉を使うことで脳の神経回路が刺激され、運動機能の改善も期待できます。
スクワットや椅子からの立ち上がり練習など安全で簡単な運動を定期的に行うことが効果的。
日常生活の自立を支え、症状の進行を遅らせることに繋がることが期待できます。
基本動作練習
パーキンソン病のリハビリにおいて基本動作練習は重要です。
例えば、座る・立つ・歩くなど、日常生活の動作に必要なスキルを維持・改善します。
患者さんが生活動作に伴う固縮やバランスの問題を克服できるようにするためには、繰り返し練習することが必要。
立ち上がり動作や歩行訓練では、体幹筋の強化と関節の可動域を広げる訓練が効果的です。
また、歩行の安定や転倒予防を目的とした練習には、介助者や補助具を活用し、安全に行うことが求められます。
患者の現在の症状に応じて無理のない方法で進めることが大切です。
歩行練習
パーキンソン病のリハビリでは、歩行練習が重要です。
すくみ足や小刻み歩行、転倒リスクを軽減するために、視覚的なガイド(床に線を引くなど)やリズムに合わせた歩行訓練が効果的。
バランストレーニングを組み合わせることで、安定性を高められます。
また、転倒防止や歩幅改善のために、歩行を始める前に特定の準備動作を取り入れることも推奨されています。
こうした練習を継続することで、自信を持って生活を楽しめるようサポート。
日常動作練習
パーキンソン病における日常動作練習は、生活の自立を維持するために重要なリハビリの一環です。
例えば、立ち上がりや歩行、食事などの基本動作を再学習することで、動作の効率化と安全性を向上させます。
特に「すくみ足」や動作の遅延を改善するために、床に目印を付けたりリズムに合わせた動作を取り入れることが効果的。
また、複数の動作を一度に行うのではなく、一つずつ確実に進めることで動作の円滑化を図ります。
この練習は患者の進行度に応じて個別化されることが大切です。
作業療法
パーキンソン病の作業療法は、日常生活の質(QOL)を向上させるために欠かせません。
この療法では、日常動作の再学習や筋力向上、柔軟性の改善を通じて、自立した生活を支援。
たとえば、服の着脱や食事、入浴などの基本的な動作を安全かつ効率的に行えるよう訓練します。
また、歩行やバランス改善のためのトレーニングや、転倒防止を目的とした環境調整も含まれます。
患者さん個々の症状やニーズに応じたアプローチが行われるのが特徴です。
この取り組みは、身体的機能だけでなく心理的安定感もサポートします。
呼吸訓練
パーキンソン病の呼吸訓練は、呼吸筋力を維持・向上させ、日常生活の質を高めるために重要です。
具体的には、深呼吸や腹式呼吸、口すぼめ呼吸を練習し、酸素摂取を効率化します。
また、咳嗽訓練や呼吸補助器具を使用して痰の排出を促進し、誤嚥性肺炎のリスクを軽減。
これらの訓練を通じて、呼吸困難の症状を和らげ、不安感を軽減することが可能です。
患者さんの状態に合わせた個別プログラムが効果的で、リハビリ専門家の指導の下、無理なく続けることが大切です。
構音訓練
構音障害は、パーキンソン病の患者さんにとってコミュニケーションの難しさを引き起こす重要な症状のひとつです。
リハビリでは、「声を大きく保つ」「抑揚をつける」などの技術を練習し、声の明瞭性と発話の力を改善することを目指します。
例えば、深呼吸を伴う発音練習や、指折りで単語を区切りながら話す練習が有効。
また、リズムを活用し、メトロノームに合わせて発声する方法も役立ちます。
これらの取り組みは、生活の質(QOL)の向上を支え、社会参加の可能性を広げるための鍵となります。
患者さんの症状やニーズに合わせた個別プログラムがとても大切です。
嚥下訓練
嚥下訓練は、パーキンソン病患者の飲み込みの安全と効率を向上させるための重要なリハビリ方法です。
具体的には、深呼吸や咀嚼訓練、舌の可動域を広げる練習が含まれます。
これにより、食べ物の喉への移動をスムーズにし、誤嚥のリスクを軽減。
例えば、メンデルソン手技や頸部挙上運動といった専門的なテクニックが用いられることもあります。
また、嚥下造影検査(VF)のフィードバックを活用して訓練を進めることで、より効果的な結果を得ることが期待されます。
嚥下機能の維持は、食事を楽しむためにも日々のリハビリを欠かさないことが重要です。
音楽療法
音楽療法は、パーキンソン病患者のリハビリにおいて重要な役割を果たします。
リズムやメロディが神経系に働きかけ、歩行のリズム安定や発声改善をサポート。
例えば、好きな曲を聴くことでモチベーションが向上し、声を出して歌うことで呼吸や発声筋を活性化させる効果があります。
また、リズム音楽を用いた歩行訓練は、すくみ足の緩和やバランス改善につながる場合があるのもポイントです。
音楽療法は感情面にも働きかけ、不安や抑うつ症状の軽減が期待されます。
個々に適した音楽や訓練プランが治療効果を最大化してくれることも期待できます。
パーキンソン病の治療をサポートするストレスフリー療法

ストレスフリー療法は、心身のリラックスを促進し、生活の質(QOL)を向上させる重要な方法。
この療法では、ストレスフリー療法とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30分~60分照射する温熱療法です。
これにより血流の促進やストレスホルモンの低減が期待できます。
深呼吸や瞑想などのリラクゼーション技法も組み合わせることで、その効果をさらに高めることも。ストレスフリー療法は安全で継続しやすいので、穏やかな環境で行うとより効果的です。
また、実際の診療実績も多数ありますので気になる方は実例を参考に、施術を検討してみてはいかがでしょうか。
当療法に特化した専門クリニックとして信頼されているのが、「銀座数寄屋橋クリニック」です。
公式サイトにてさらに詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ

パーキンソン病のリハビリは、日常動作や呼吸、嚥下、構音障害などを対象に多岐にわたり、音楽療法やストレスフリー療法も効果的です。
それぞれ個別調整が可能で、身体機能の向上のみならず、不安や抑うつ軽減といった精神的ケアも含まれます。
これらは生活の質(QOL)を支える重要な役割を果たし、患者さんの自立や社会参加を促進します。
適切な治療やリハビリを取り入れ、早期発見・早期対処で病気になっても、自分らしい生活を楽しめるよう頑張りましょう。






