歩きづらい、手がこわばる…そのような変化を感じていませんか?
レビー小体型認知症では、歩行障害や手の震えなどパーキンソン症状が現れることがあります。
例えば、転倒や嚥下障害などがあり、日常生活に影響する症状も少なくありません。
そこで今回は、レビー小体型認知症を詳しく説明し、いくつかの症状をご紹介していきます。
もしかして?と気になった方は、ぜひ最後までご覧ください。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

レビー小体型認知症とは一体どんな病気なのか
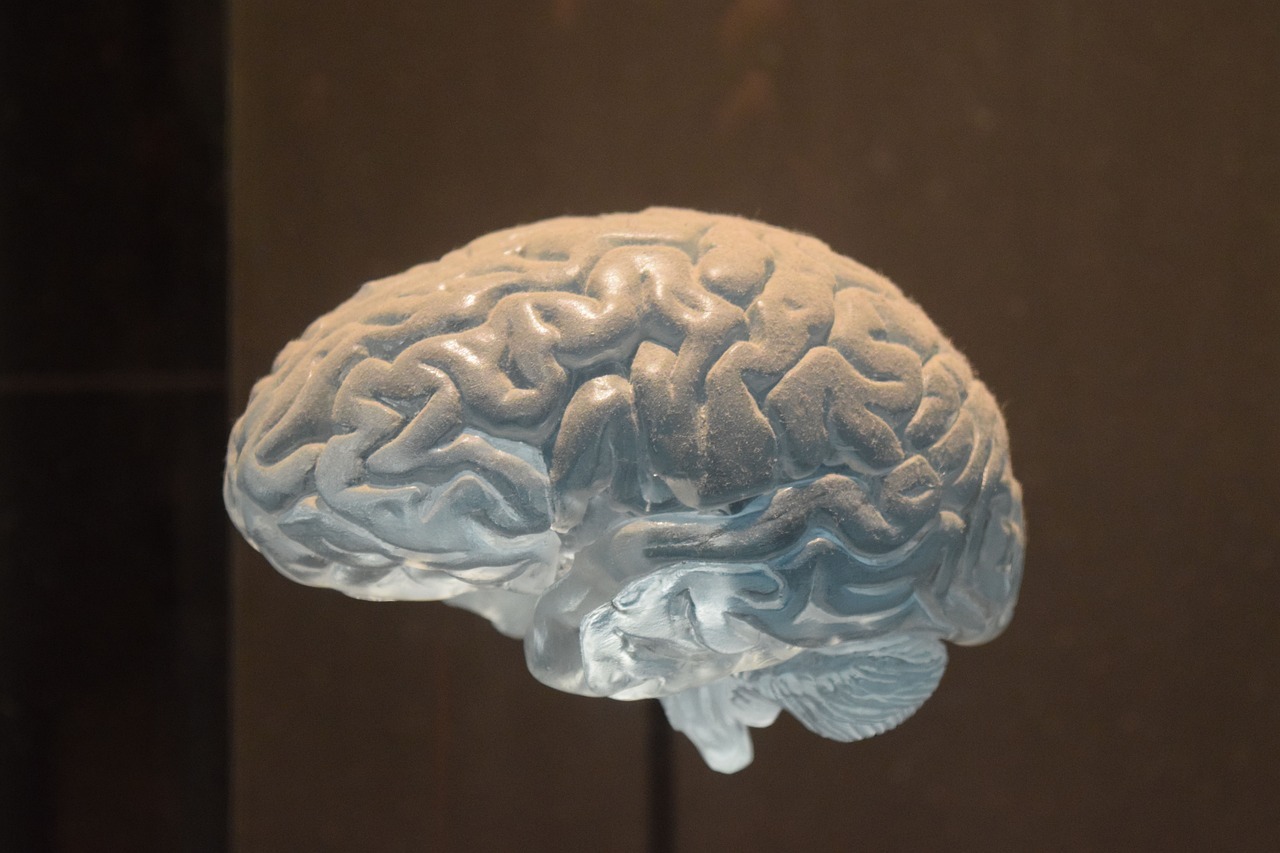
レビー小体型認知症は、認知機能の変動や幻視とともにパーキンソン病に似た症状が現れるのが特徴です。
表情が乏しくなる(仮面様顔貌)、歩きにくさや手足のこわばりなど、ふだんの暮らしの動きに影響することも。
このような症状は、脳内でドーパミンやノルアドレナリンなどの神経伝達物質が不足して起こると考えられています。
進行に応じて転倒や飲み込みの難しさが目立つようになり、日々の暮らしにさまざまな支障が出ることがある病気です。
レビー小体型認知症に見られるパーキンソン症状とは

歩行や動作に影響するパーキンソン症状が現れることがあるのが、レビー小体型認知症です。
安静時振戦や筋固縮、動作緩慢、姿勢反射障害や小字症があります。
また、小声症や脂漏性顔貌、突進歩行、すり足歩行、ピサ徴候、嚥下障害など症状はさまざま。
そこで、レビー小体型認知症に見られるパーキンソン症状を、詳しく解説していきます。
不安な方はぜひ参考にしてください。
安静時振戦
安静時振戦とは、座って何もしていないときや寝ているときに、手足が小刻みに震えます。
レビー小体型認知症に見られるパーキンソン症状のひとつで、パーキンソン病でも代表的な症状です。
原因は脳内のドーパミン不足などによる神経の異常と考えられています。
歩行中や手を使おうとするとき、震えが止まることが多いのが特徴です。
震えが気になり、不安を感じる方も。
ですが、薬による治療と周囲の支えで安心できる暮らしを続けることも可能になってきています。
筋固縮
筋固縮(きんこしゅく)とは、筋肉のこわばりで、レビー小体型認知症などで見られるパーキンソン症状のひとつです。
筋肉がこわばり、体が思うように動かしにくくなる状態や歩行がぎこちなくなり転びやすくなることもあります。
こわばった筋肉は、動かすと歯車のようにカクカクと動く「歯車現象」や、ずっとこわばりが続く「鉛管現象」が見られることも。
脳内のドーパミン不足が原因とされ、薬による調整や周囲の理解がとても大切です。
動作緩慢
動作緩慢は、体の動きがゆっくりになり日常の動作が遅くなります。
思うように動けなくなる状態です。
例えば、服を着る、ボタンを留める、歩き始める、食事をするなどの動作に時間がかかり、不安やもどかしさを感じる方もいます。
原因は、脳内の神経伝達の異常により、体を動かす指令がうまく伝わらなくなるため。
ゆっくりペースを大切にしながら過ごすことや、必要に応じて薬の調整やリハビリ、また周囲の理解と支えが安心につながります。
姿勢反射障害
姿勢反射障害は、レビー小体型認知症などで見られるパーキンソン症状のひとつです。
体のバランスがとりにくくなり、立っているときに少し押されるだけでふらつき、転んでしまうことがあります。
また、転倒したあと自分で体制を立て直すのが、難しくなるのも特徴。
進行すると、この症状が現れ歩行に不安を感じる方も増えます。
この状態は重症度分類でヤールⅢ度と呼ばれ、転倒の危険が高まるため難病の治療費が補助される対象です。
原因は脳内の神経伝達の異常と考えられ、薬やリハビリ、身近な支えが力になることも少なくありません。
小字症
パーキンソン病の主な症状で、無動(動作が遅く、動きが小さくなる)が小字症の原因のひとつです。
文字を書くとき徐々に字が小さくなっていく状態で、原因は脳内の神経伝達物質(ドーパミン)の不足が考えられています。
本人も気付かないうちに字がだんだん小さくなる状態で、書くことに自信をなくしてしまう方も。
手先の細かい動きをうまく調整できなくなり、書類などを書くのに時間がかかり思うように書けないことで不安になる方もいます。
小声症
小声症は、レビー小体型認知症やパーキンソン症状のひとつで、声が小さくなり相手にとって聞き取りづらくなる症状です。
大きな声が出せなくなる、抑揚のない話し方や話し始めが遅くなるなどの特徴がみられることも。
また、話し出すと急に早口になる方もいます。原因は脳内の神経伝達の異常によるもので、声を出す筋肉の動きがうまく調整できなくなるためと考えられています。
このため、会話がうまくいかず不安を感じる方も少なくありません。
周囲の方の理解や支えが安心につながります。
脂漏性顔貌
脂漏性顔貌(しろうせいがんぼう)は、レビー小体型認知症やパーキンソン病の非運動症状で見られる特徴のひとつです。
自律神経の障害で体表の分泌物が多くなることで、顔が脂っぽくテカテカした印象になり、表情が乏しくなるのが特徴に挙げられます。
脳内の神経伝達の異常によって皮脂の分泌が調整しにくくなるためと考えられています。
表情筋の動きが低下し笑顔などの感情が顔に表れにくくなることもあるため、周囲から気持ちが伝わりにくくなることも。
必要に応じて、表情筋を意識的に動かす訓練や皮脂のケアが生活上の安心感や清潔感の維持に役立ちます。
仮面様顔貌
顔の表情が乏しく、まるで仮面をかぶっているかのように見えるパーキンソン病やパーキンソン症候群に見られる症状です。
仮面様顔貌(かめんようがんぼう)は、表情筋の動きが鈍くなります。
笑顔や怒った顔などの感情を出すことが難しいのが特徴。
初期のうちはご家族が表情の変化に気付くことがあります。
通常よりまばたきの回数が減り、一点を見つめているように見えることも特徴です。
他には、口を閉じた状態が続くことで口角が下がり、声が小さく抑揚のない話し方になることも。
仮面様顔貌は、脳の神経伝達物質のドーパミン不足により、引き起こされます。
突進歩行
突進歩行も症状のひとつです。
体が前のめりの姿勢になり、歩くうちに歩幅が小さくなる小刻み歩行とともに、次第にスピードが増します。
また、自分の意志で止まれなくなるのが特徴。
後ろ向きに歩くときも、同じように体が止まらなくなることがあります。
特に狭い場所や曲がり角でつまずきやすく、転倒のリスクが高いです。
姿勢や歩き方を少し意識することやリハビリ、お薬の調整、周りの方の支えが不安を和らげる方法に挙げられます。
すり足歩行
すり足歩行は、レビー小体型認知症などのパーキンソン症状でよく見られる歩行障害の特徴です。
歩くときに足がしっかり持ち上がらず、床をすりながら歩くようになります。
突進歩行やすくみ足が加わるのが、進行すると現れる症状。
歩幅は徐々に狭くなり、止まりたいときに止まれず、転倒の危険が高まります。
また、狭い場所や方向転換のときには、少しの段差やじゅうたんなどの端につまずきやすく、転倒の原因になる点に注意しましょう。
リハビリでは、足を高く上げる練習やバランス訓練、歩行補助具の活用が有効です。
ピサ徴候
体が左右どちらかに傾いてしまう状態がピサ微候で、レビー小体型認知症やパーキンソン症状のひとつ。
立っているときや歩行中、身体が左右どちらかに傾いてしまう状態で転倒のリスクも高くなります。
ピサの斜塔のように身体が斜めになってしまうため、この名前がついています。
考えられている原因は、脳内の神経伝達の異常や筋肉のバランスの崩れです。
また、長時間座っていても傾くことがあります。
歩くときにふらつきや転倒の危険が高まるため、周囲の支えやリハビリ、必要に応じて薬の調整などが重要。
嚥下障害
レビー小体型認知症などで見られるパーキンソン症状のひとつで、食べ物や飲み物をうまく飲み込めなくなる状態です。
考えられる原因は、脳内の神経伝達の異常で、飲み込む動作に関わる筋肉がうまく動かなくなるためと考えられています。
むせやすくなったり、食事に時間がかかったり食事が進まなくなったりします。
また、体力や栄養状態が心配になる方も少なくありません。
誤嚥による肺炎が起こるリスクもあるため、早めの対応が求められます。
薬の調整やリハビリ、食事の工夫で安心につながることもあります。
転倒と同じく、歩行や日常生活のサポートも大切です。
全身のコンディションを整えるストレスフリー療法

ストレスフリー療法は、体に負担をかけずに心地よい温熱刺激を与えることで、リラックスを促す温熱ケアです。
お腹の中脘、左膝外側の足三里、両足裏の特別なツボ2か所、顔の特別なツボ2か所の合計6か所に小さな導子をつけます。
30分から60分間、遠赤外線の温かな刺激をリズミカルに届け血流のめぐりをサポート。
血流の流れにやさしく働きかけ、心と体のバランスを整えたい方におすすめです。
毎日の穏やかな心身のバランスづくりに役立つことが期待されます。
癒しの時間を過ごしたい方にも、そっと寄り添うケアです。
当療法に特化した専門クリニックとして信頼されているのが、「銀座数寄屋橋クリニック」です。
公式サイトにてさらに詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ

レビー小体型認知症で見られるのは、すり足歩行や体のこわばりなどさまざまなパーキンソン症状です。
毎日の暮らしに不安をもたらすこともありますが、無理のない範囲で体調を整える工夫が安心につながります。
ストレスフリー療法は心地よい温熱刺激でリラックス感をサポート。
穏やかな時間を過ごしたい方に選ばれています。
気になる方は、ご自身の体調に合うかどうか、主治医に相談のうえで取り入れてみてください。
前向きな気持ちで、少しずつできることを積み重ねていきましょう。






