パーキンソン病や認知症は進行性の疾患で加齢とともに発症しやすくなる病気として知られており、パーキンソン病も認知症も、どちらも人生の質に深く影響を与える疾患です。
どちらも、40代を超えると発症率が増加傾向にある疾患。
加齢とともに意識したり興味を持ち始めた方も多いのではないでしょうか。
これらの疾患の基本的な知識や初期症状、生活の工夫についてわかりやすく解説します。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン病認知症とは一体何か

パーキンソン病認知症は、パーキンソン病の進行と共に現れることのある認知症です。
記憶力や判断力の低下に加え、注意力が散漫になったり、日常生活の中で混乱を感じることもあります。
主な原因としては神経伝達物質の減少が挙げられ、これが脳の機能に影響を及ぼします。
症状が進むと患者の日常生活や自立性に影響が出ることが多く、早期の診断と適切なケア、家族や専門家のサポートが重要。
パーキンソン病認知症の主な原因とは
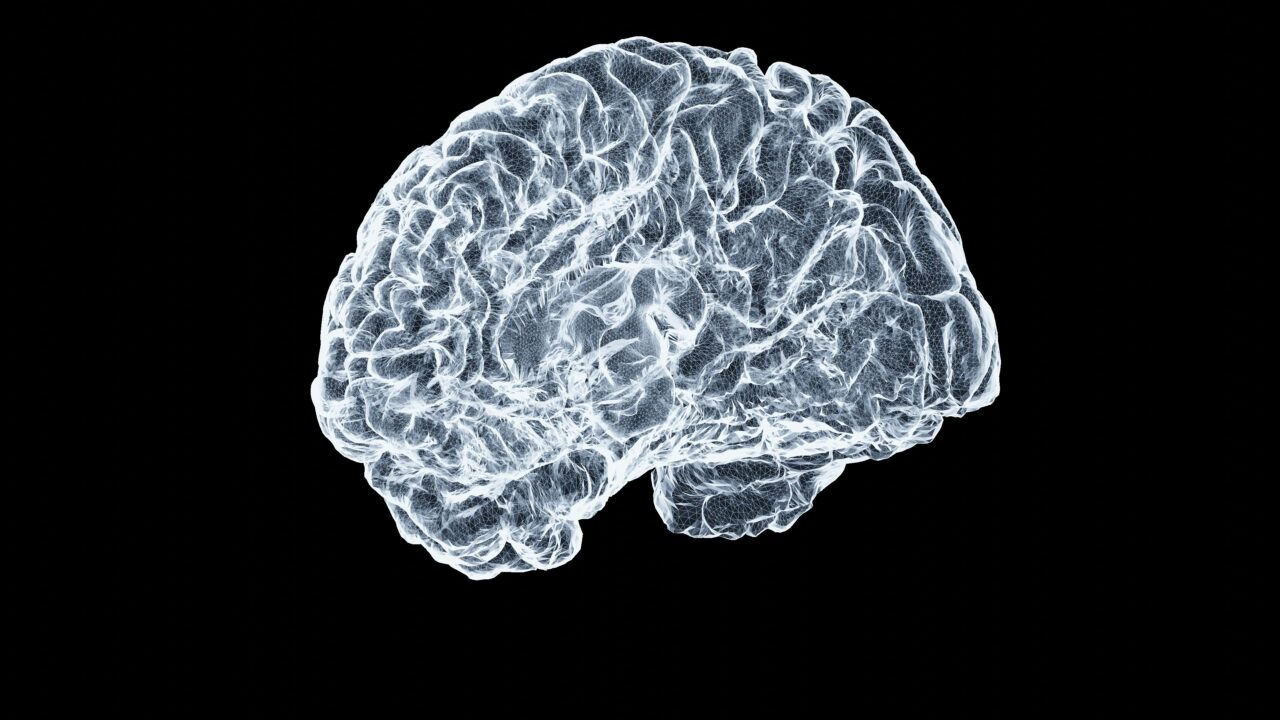
パーキンソン病認知症は、パーキンソン病の進行によって生じる認知症の一種。
脳内の神経伝達物質の異常がその主な原因とされています。
ここからは、パーキンソン病認知症の発症に関わる具体的な要因に加え、症状の進行メカニズムや科学的な背景を中心に解説していきます。
脳内の神経変性
ドーパミンを生成する神経細胞が変性・減少することで、運動機能だけでなく記憶や判断力などの認知機能にも影響を及ぼすとされています。
「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質の蓄積も神経変性を引き起こす一因とされているため、注意が必要です。
これらの変化により、認知機能の低下症状が進行し生活の質が低下するため、早期の対処と専門的なケアが重要となってきます。
脳の構造的変化
パーキンソン病認知症の原因の一つには、脳の構造的変化もあげられます。
病気の進行に伴い、大脳皮質の萎縮や、レビー小体と呼ばれる異常なタンパク質の蓄積が増加。
このような変化が神経伝達に影響を与え、記憶力や注意力、判断力の低下を引き起こします。
脳内でのドーパミン生成細胞の減少も加わり、認知機能障害を悪化させます。
これらの構造的変化は、パーキンソン病認知症の進行と症状の複雑化につながるため、注意が必要です。
レビー小体の蓄積
パーキンソン病認知症の原因の一つには、レビー小体の蓄積も挙げられます。
レビー小体とは、神経細胞内に見られる異常な円形構造物(タンパク質α-シヌクレインの集合体)。
レビー小体が脳内の神経細胞に異常に蓄積することで、神経細胞の機能を損なわせ、情報伝達を妨げます。
記憶障害や認知機能低下につながり、パーキンソン病認知症を発症させてしまいます。
これらを防ぐためには、早期診断と適切なケアが重要です。
神経伝達物質の不均衡
パーキンソン病認知症の原因の一つには、神経伝達物質が不均衡による発症も挙げられます。
ドーパミンの減少が脳内の運動を調整する能力を低下させるだけでなく、アセチルコリンと呼ばれる脳や体内で神経から神経、または神経から筋肉へ情報を伝える「神経伝達物質」が相対的に過剰になります。
記憶や注意力に影響を与えることも。
このような不均衡は、脳の情報伝達プロセスを妨げることに繋がり、パーキンソン病認知症の進行を助長することになってしまいます。
代謝異常などによる健康の問題
代謝異常などによる健康の問題も、パーキンソン病認知症の重要な原因の一つです。
特に糖や脂質代謝の問題が脳細胞に影響を与えます。
エネルギー供給の不足により神経伝達が妨げられるだけでなく、酸化ストレスや慢性炎症によって神経細胞が損傷を受け、認知機能の低下が進行します。
また、代謝異常による有害物質の蓄積が脳の構造に悪影響を与えることも。
これらの要因が複雑に絡み合い、症状を重くするため、適切な治療と生活改善が非常に重要です。
パーキンソン病認知症になると現れる症状

ここまで、パーキンソン病認知症の概要と発症の原因について解説してきました。
では、実際にパーキンソン病認知症を発症するとどのような症状が現れるのでしょうか。
ここからは、パーキンソン病認知症になると現れる症状について解説していきます。
記憶障害
パーキンソン病認知症を発症すると記憶障害を引き起こします。
特に短期記憶や新しい情報の保持、そしてこれを必要とする日常のタスクに影響を及ぼしやすいといわれています。
パーキンソン病認知症の記憶障害は脳内のドーパミン不足や、アルツハイマー型認知症とは異なる脳の変化に関連していることが特徴。
たとえば、日常的な予定や人との約束を忘れやすくなったり、作業手順を思い出せなかったりすることが見られます。
また、記憶障害と併せて注意力の低下や空間認識の混乱も観察されることが多いです。
集中力の低下
パーキンソン病認知症を発症すると、集中力の低下が引き起こされます。
この集中力の低下は、注意力を維持する能力が著しく減退する状態を指します。
例えば、複数のタスクを同時進行で行うことが困難になり、話し手の言葉に集中することができなくなることも。
この症状は脳の神経伝達物質であるドーパミンの不足や神経回路の損傷と関連している場合が多いといわれています。
集中力が低下することにより、計画性の欠如や記憶力との連動した障害が生じることもあります。
判断力の低下
パーキンソン病認知症になると、判断力の低下も顕著に現れ、複雑な状況や問題に対して適切な選択を行うことが難しくなることが増えるといわれています。
日常生活では買い物での予算管理がうまくいかなくなったり、交通ルールを適切に判断できなくなる場合も。
この症状は、脳の認知機能をつかさどる領域の変性や、情報処理能力の低下に関連しているとされています。
判断力の低下が進むことで、本人のみならず介護者や周囲の人々にも負担がかかることが増えることが考えられます。
精神症状
不安感や抑うつなどが現れる方も多く、感情の起伏が大きくなることもあります。
一部の方々は幻覚や妄想といった症状を経験することがあり、それが日常生活に影響を及ぼす場合も。
精神的な影響の背景には、脳内の神経伝達物質や神経回路の変化が関係している場合があるといわれています。
生活の制約や孤独感も生じやすくなり、パーキンソン病認知症の症状を悪化させる要因となることがあります。
言語能力の変化
パーキンソン病認知症の言語能力の変化には、言葉を理解したり、適切に表現したりする能力に影響を及ぼします。
この症状では、言葉を探すのに時間がかかったり、複雑な文章を理解するのが難しくなったりすることがあります。
また、思考が遅れることで、会話のテンポが合わなくなり、意図をうまく伝えられない場面も生じることも。
さらに、発話の流暢さが減少し、単語選択の精度が低下することもあります。
社会的孤立
パーキンソン病認知症を発症すると、社会的孤立を感じる方も多いといわれています。
パーキンソン病認知症に伴う社会的孤立は、病気の進行による身体的・認知的制約が、人間関係や社会的な交流に影響を及ぼすことが背景にあります。
例えば、発話や動作の困難から他者とのコミュニケーションが減少したり、不安感や抑うつの症状が外出や対人活動を妨げる要因となることも。
この孤立感は、さらに精神状態に影響を与え、症状の悪化を招く負の連鎖を生む可能性があります。
パーキンソン病認知症になった場合におけるサポートの方法

パーキンソン病認知症では、患者の症状に合わせた支援が欠かせません。環境調整や医療専門家の助言を基にしたケアが重要です。また、家族や介護者の協力が患者の安心感と生活の質を高める鍵となります。
ここからは、パーキンソン病認知症になった場合におけるサポートの方法を紹介します。
薬物治療
パーキンソン病認知症の薬物療法には、主にコリンエステラーゼ阻害薬が使われます。
コリンエステラーゼは脳の神経伝達物質を分解してしまう酵素。
この働きを阻害することで、アセチルコリンという神経伝達物質の働きを助け、記憶力や認知機能の維持に寄与します。
一部の患者にはメマンチンも処方され、思考の明瞭さを支える効果があります。
ただし、薬物選択は患者ごとの症状に合わせて慎重に行い、副作用や他の薬との相互作用に注意が必要です。
定期的な診察と調整が治療成功の鍵となります。
認知機能強化トレーニング
パーキンソン病認知症の治療には認知機能強化トレーニングも重要です。
認知機能強化トレーニングは記憶力、注意力、判断力などの維持と改善を目指したプログラム。
患者個人のニーズに合わせて、言語課題やパズル、脳を刺激し、注意力を高めるタスクなどを組み合わせて実施されます。
継続的な実践が脳の活性化を促し、日常生活での問題解決能力の向上にも繋がります。
また、トレーニングには社会的な交流を含めることで、感情面のサポートも可能です。
生活習慣の改善
パーキンソン病認知症の治療では、生活習慣の改善が症状の進行を抑え、QOL(生活の質)を向上させる上で重要です。
適度な運動は脳の血流を促し、認知機能や運動機能の改善に効果的。
また、バランスの取れた食事は脳に必要な栄養を供給し、体力維持にも役立ちます。
質の良い睡眠とストレス管理も神経系への負担を軽減し、治療効果を高めるのもポイントです。
これらの取り組みを薬物療法と組み合わせることで、より良い治療結果が期待できます。
社会的サポート
パーキンソン病認知症の治療において、社会的サポートは患者のQOL(生活の質)向上に欠かせない要素です。患者が孤立せず、地域や家族、医療チームとのつながりを持つことで、精神的な安心感と自立を支えます。例えば、デイサービスや地域の患者会への参加はコミュニケーションの促進だけでなく、認知機能への刺激にも役立ちます。また、専門家によるカウンセリングや介護者への教育を通じて、患者の感情的な安定やスムーズな治療が可能になります。
このような社会的支援は、患者とその家族双方にとって大きな力となります。
生活環境の調整
パーキンソン病認知症の方にとって、生活環境の調整が患者の安全性と自立性を支える重要な要素です。
パーキンソン病認知症になると、筋肉が意図せず震えたりこわばったりなどの症状が現れるため、転倒などの危険が増す傾向にあります。
治療やリハビリを阻害してしまう要因になってしまうため、生活環境の調整も重要。
例えば、段差を減らしたり手すりを設置することで、転倒リスクを軽減し移動を容易にします。
家具の配置を工夫し、動線を広げることで日常生活がスムーズになります。
夜間の移動にはセンサー付きライトやリモコン操作の電灯を導入するなど、視覚的な配慮も大切です。
専門家の介入
パーキンソン病認知症の治療では、医師や理学療法士の定期的なケアが重要です。
医師の診察により薬物治療や症状管理が最適化され、進行の抑制や副作用の確認が行われます。
一方、理学療法士による運動療法やリハビリは、運動能力の維持・改善に寄与。
これにより転倒リスクが減り、自立した生活が可能になります。
また、認知症を伴う場合には、認知機能を刺激するリハビリが効果的です。
これらの専門ケアを継続することで、患者の身体機能の維持と生活の質が向上します。
ストレスフリー療法
パーキンソン病認知症の治療には、ストレスフリー療法も効果が期待できます。
ストレスフリー療法とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30分~60分照射する温熱療法。
ストレスホルモンであるコルチゾールを減少させ、血流を増加させて神経や運動機能を改善します。
さらに、情緒の安定や認知機能の向上も期待できるため、患者の全体的な身体機能の維持や生活の質を高める効果があります。
当療法に特化した専門クリニックとして信頼されているのが、「銀座数寄屋橋クリニック」です。
公式サイトにてさらに詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ

パーキンソン病認知症は、認知機能と運動機能の両方に影響を与える疾患です。
薬物療法を中心とした治療で、認知機能の維持を目指します。
また、認知機能強化トレーニングや生活習慣の改善、社会的サポート、生活環境の調整も治療を助けてくれる重要な要素。
さらに、医師や理学療法士による定期的なケアや、ストレスフリー療法などが症状を改善する効果が期待できます。
病気であっても自分らしい生活を諦めず、良い人生を送りましょう。






