残念ながらパーキンソン病は一度発症すると完治が難しい病気です。
ゆっくりと進行するのが特徴ですが、薬や手術で症状を抑えられます。
今回は、パーキンソン病が進行すると症状がどのように進むのかを段階に分けて紹介します。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン病とは一体どんな病気なのか
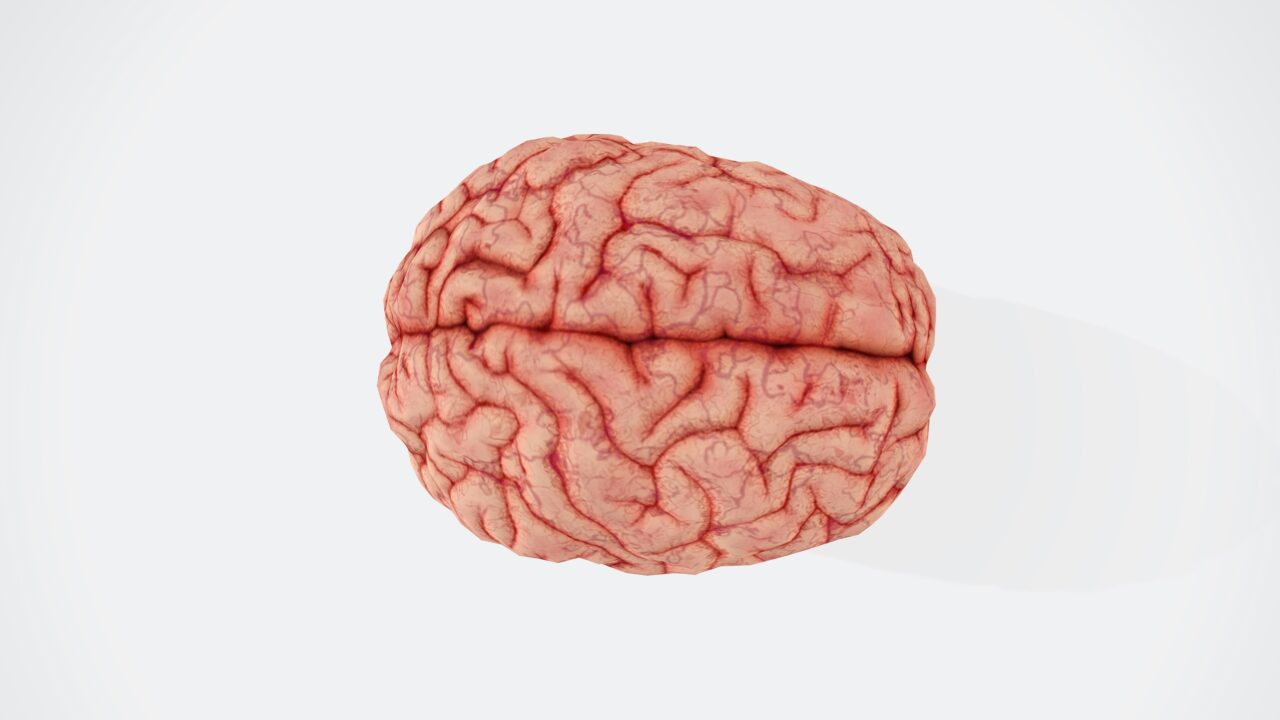
パーキンソン病は脳からのドーパミンが何らかの原因により減少し、運動機能や精神面に影響を及ぼす病気です。
体が動かしにくくなったり、ふるえたりする運動面だけでなく、鬱や認知機能など精神面にも影響が出ます。
50代以上で発症する人が多く、まれに40代以下の若い人もいて若年性パーキンソン病と呼ばれます。
パーキンソン病の症状の進行度を示す指標

パーキンソン病の進行度合いを示す指標には、通常ホーン・ヤールの重症度分類と厚生労働省が定めた生活機能障害度分類を用います。
それぞれどのような分類わけがされているのか説明します。
ホーン・ヤールの重症度分類
ホーン・ヤールの重症度分類では、パーキンソン病の進行段階を5段階に分けています。
ふるえなどの症状が片側のみの場合はⅠ度、両側に見られたらⅡ度になり、さらに症状が進行して体のバランス障害があらわれたらⅢ度、介助が必要な場合はⅣ度、車椅子や寝たきりの生活になったらⅤ度になります。
治療により、Ⅲ度からⅡ度に改善する可能性も。
パーキンソン病を発症した人全員がⅣ度やⅤ度の状態になるわけではありません。
厚生労働省の生活機能障害度分類
生活機能障害度分類は厚生労働省が定めた分類法で、3段階に分かれています。
1度は日常生活や通院にほとんど介助を要さない程度でホーン・ヤールのⅠ、Ⅱ度に適応します。ホーン・ヤールのⅢ、Ⅳ度に対応する2度は日常生活で部分的に介助が必要になった状態です。
3度はホーン・ヤールの5度に対応していて、全面的に介助が必要な状態を指します。
ホーン・ヤールでⅢ度以上、生活機能障害度分類で2度以上になると、難病医療費補助制度を受けられます。
パーキンソン病が著しく進行した際に生じる問題

パーキンソン病が進行すると、症状が進むだけでなく、薬の副作用や精神面にも影響が出てきます。
パーキンソン病が著しく進行した際に生じる問題を解説します。
ウェアリングオフ現象
ウェアリングオフ現象とは、薬の長期服用によって発生する副作用です。
パーキンソン病の治療薬として一般的なL-ドパは、筋肉のこわばりやふるえが改善する一方、何年も服用し続けていると薬の効果が弱まってきます。
飲んで2〜3時間すると薬の効能が切れ、治療前の状態に戻ってしまいます。
1日のなかで薬が効いている時間と効いていない時間を繰り返すので、服用量や頻度、薬の種類を変えて対処することが重要。
ジスキネジア
L-ドパの長期服用による副作用は他にジスキネジアがあります。
ジスキネジアとは薬が切れたタイミングで現れやすいです。
体が自分の意思とは関係なく、くねくね動いたり、口がもごもごしたりする症状をいいます。
L-ドパはパーキンソン病で減少したドーパミンを補充する薬ですが、5年以上服用すると高確率でジスキネジアを発症。
また、痛みをともなう筋肉の収縮や硬直を繰り返すジストニアという症状が出る可能性もあります。
認知症
パーキンソン病が進行すると認知機能障害を起こす人がいます。
認知機能障害とは、短期記憶障害や集中力、注意力の低下、言語障害などです。
アルツハイマーと間違われますが、パーキンソン病は運動障害が先行し、のちに認知機能障害を発症します。
ドーパミン減少だけでなく、神経伝達物質の不均衡化やレビー小体の蓄積により神経細胞が死んで機能しなくなるなども原因。
パーキンソン病患者の40%の人にみられ、発症後10〜15年後に症状が出てきます。
進行度に応じたパーキンソン病におけるサポートの内容

パーキンソン病が進行したらどのような症状が現れるのかに加え、どのようなサポートを受けたらよいのか3段階に分けて説明します。
初期
パーキンソン病を発症したらすぐに症状が進行するわけではありません。
パーキンソン病は何年もゆっくりとかけて進行するのが特徴です。
なかには、初期症状に気付かない人もいます。
初期は、軽度の手足のふるえや筋肉のこわばりが見られます。
日常生活にほとんど影響はありませんが、繊細な手作業が若干困難になり、右手が使いにくいなどの症状を訴える人も。
しかし、MRIを撮っても異常が見られず発見されないケースも多くあります。
中期
パーキンソン病が進行すると、筋肉のこわばりやふるえがひどくなって動作の遅さやバランスを保つのが難しくなってきます。
歩行や日常生活にも支障が出始め、本人だけでなく周囲も異変に気づき始めます。
足が床にへばりついたように感じ、前に進めなくなるすくみ足や小刻み歩行、突進減少などがあらわれ、転倒のリスクが高くなるので注意が必要です。
転倒防止のために補助具を使ったり、家のなかに手すりをつけたりして予防しましょう。
末期
パーキンソン病がさらに進行して末期の状態になると、重度の運動障害やバランスの大幅な低下が見られるようになります。
また運動障害だけでなく、認知機能や睡眠、精神面などの非運動症状にも障害が見られます。
具体的には声が小さくなったり、便秘になったり、鬱状態になったりすることも。
日常生活にも影響が大きく、介護やリハビリなど大部分でサポートが必要です。
パーキンソン病の治療法

パーキンソン病の治療法は主に薬物治療と手術です。
どちらもメリットとデメリットがあり、副作用が少ない治療法として、近年はストレスフリー療法も注目されています。
それぞれどのような治療法か説明します。
薬物治療
パーキンソン病の治療には薬物療法が一般的です。
ドーパミン欠乏が原因とされているパーキンソン病の治療薬はさまざま。
ドーパミンを直接補充するものやドーパミンを分解する酵素の働きを阻害するものがあります。
それぞれ一長一短あり、医師が患者の年齢や状態、進行度合いによって処方する薬を選びます。
長期服用によって副作用が出やすい薬もあり、症状の進行度合で薬の量や飲む頻度を調整。
手術
脳深部刺激療法(DBS)は脳の骨に小さな穴をあけ、電極を埋め込みます。
電気刺激を与え、パーキンソン病で崩れた神経回路のバランスを取り戻す手法です。
パーキンソン病の根本改善にはなりませんが、ジスキネジアを発症した人に有効な方法。
DBSは特殊な技術を要するため限られた病院でのみ治療を受けられます。
DBSは手術合併症が少ない・保険適用で受けられるなどメリットもありますが、リスクをともなうため主治医と相談してから受けることが大切です。
ストレスフリー療法
ストレスフリー療法とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30〜60分照射する温熱療法です。
血流の向上により、冷え性や睡眠障害が改善されます。
パーキンソン病はドーパミンの欠乏が原因と考えられていますが、症状が改善した例が複数存在。
脳への血流改善によってドーパミン生成が促されている可能性が考えられます。
ストレスフリー療法はドーパミン減少の原因にもなりえるストレスホルモンのコルチゾールを低下させる効果があり、パーキンソン病の予防にも役立つ可能性があります。
当療法に特化した専門クリニックとして信頼されているのが、「銀座数寄屋橋クリニック」です。
公式サイトにてさらに詳しい情報をご覧いただけます。
パーキンソン病の早期発見・治療が重要

パーキンソン病は決して怖い病気ではなく、死ぬ病気でもありません。
ただし、国に難病指定されている病気で完治は難しく、長く付き合うことが重要です。
パーキンソン病の治療薬はさまざま開発されていて、早めに服用すると症状の進行を抑えられます。
本人や周囲も気付きにくく、動作に集中すると症状が改善する傾向があるため、診察時に症状が出にくく発見が遅れるケースもあります。
早期の治療で症状の進行を止められるパーキンソン病の疑いが少しでもあれば早めに受診をしましょう。
まとめ

パーキンソン病はゆっくりと進行する病気で、受診が遅れがちな病気です。
早めの治療で症状の改善や進行を抑えられます。
治療法は薬物療法や手術がありますが、いずれもリスクが高く、近年は副作用の少ないストレスフリー療法が注目されています。
パーキンソン病の疑いがある場合は、早めに受診をしてください。






