パーキンソン病は運動障害の他に、認知症や精神症状を引き起こすこともあります。
性格が変わり、人格に影響が出るの?と感じる背景には、脳の変化が関係している場合も。
そこで今回は、パーキンソン病を詳しく説明し、人格障害や性格の変化が起きる原因を併せて解説します。
変化に戸惑い悩まれている方が、少しでも安心できるようご紹介していくのでぜひ、参考にしてください。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン病とは一体どんな病気なのか

パーキンソン病は、軽い症状で始まり、ゆっくりと進行していく病気です。
初期には、多少の震えや筋肉のこわばりなどの症状が現れます。
高齢者の発症が多く、ゆっくりとした進行速度ですが、症状が進行していくと立つことも一人では困難となり、介護が必要です。
また、動きが緩慢となり素早い動作ができないことで、家にひきこもることが多くなると認知症の合併が生じる場合もあります。
パーキンソン病認知症になると人格障害が起きる場合がある

感情の起伏が激しくなる衝動的な行動や意欲の低下(アパシー)のような変化が現れることがあります。
これは、パーキンソン病が進行し認知症をともなうからです。
パーキンソン病の他の症状が現れてから、10年から15年後に発症するのが一般的。
今までとは違う人格障害は、本人の性格というより考えられるのは脳神経細胞の萎縮や治療薬の影響です。
これらの症状は、パーキンソン病患者の約40%から50%に見られ心理的ストレスなども複雑に関わる結果として生じます。
パーキンソン病の進行による人格障害で家族の方は、これまでの性格の違う様子に戸惑うことがあるでしょう。
身近な人が病気として現れていると受け止め、本人を責めずに薬や心理サポートを積極的に利用することが大切です。
パーキンソン病の精神症状

パーキンソン病では、幻覚が見られることがあります。
実際に存在しない物が見えたり聞こえたりする症状です。
また、気分が落ち込む抑うつや、根拠のない思い込みの妄想記憶低下や判断低下の認知機能障害が現れることも。
進行すると日常生活への影響が大きくなる場合もあるこのような症状を、詳しくご紹介していくのでぜひ、参考にしてください。
幻覚
パーキンソン病は、進行にともなって「幻覚」が現れることがあります。
多くが視覚的な幻覚です。
症状は、実際には存在しないものが見えます。
例えば、人や動物、物体が見えるなどの症状が見られ、これらの症状が強く出るのは夕方や夜にかけてです。
本人にとって、現実との区別がつきにくいこともあります。
考えられる原因は、薬の副作用や脳内の神経伝達物質の変化です。
周りの方が落ち着いて対応することや、医師との連携で適切な治療が求められます。
抑うつ
パーキンソン病では、多くの方が心の面でも抑うつが生じます。
セロトニンの減少などの神経伝達物質の変化です。
また、病状の進行にともなうストレスや診断により、引き起こされることも。
抑うつが続いてしまい、物事への意欲低下で気分が沈みやすくなり、日常生活に支障をきたすことも。
心の変化は本人の性格のせいではなく、病気によるものと理解しましょう。
安心への一歩は、早めの専門医やカウンセリングです。
また、心のケアも取り入れていくことをおすすめします。
妄想
パーキンソン病では妄想が見られることがあります。
進行期に特に多いのは、”誰もいないのに話し声や気配を感じる”など根拠のない思い込みや被害妄想的な考えが現れます。
この背景には、治療薬(ドーパミン)の影響や脳内の化学バランスの変化、神経細胞の変性があります。
妄想はパーキンソン病の症状で本人の性格が変わったわけではありません。
そのため本人もご家族も戸惑いや不安を感じやすいです。
幻覚や妄想は、抗パーキンソン病薬(治療薬)を変更したり減らしたり中止することで症状にも変化が見られます。
治療薬の中止ができない場合も、症状を和らげるための薬が利用できます。
専門医と相談し、適切な薬物調整や心理的サポートが不可欠です。
一人で抱え込まず、対策を一緒に考えていくことで安心につながります。
認知機能障害
パーキンソン病では、運動症状の他、記憶力や判断力の低下により認知機能障害が現れることがあります。
予定を忘れやすくなる、物を置いた場所がわからなくなるなどは初期症状です。
進行すると計画を立てたり、複数の作業を同時におこなうなどが難しくなります。
このような症状は、脳内の神経細胞の変性やドーパミンの他、アセチルコリンなど神経物質のバランスの変化によるものです。
認知機能障害は、自立や安心感を保ち生活できるよう早期に気付き適切なサポートを受けることが必要。
また、日常生活の工夫や、環境を整えることなどがあり、医師や専門職との連携が大切です。
パーキンソン病で性格の変化が起きる原因
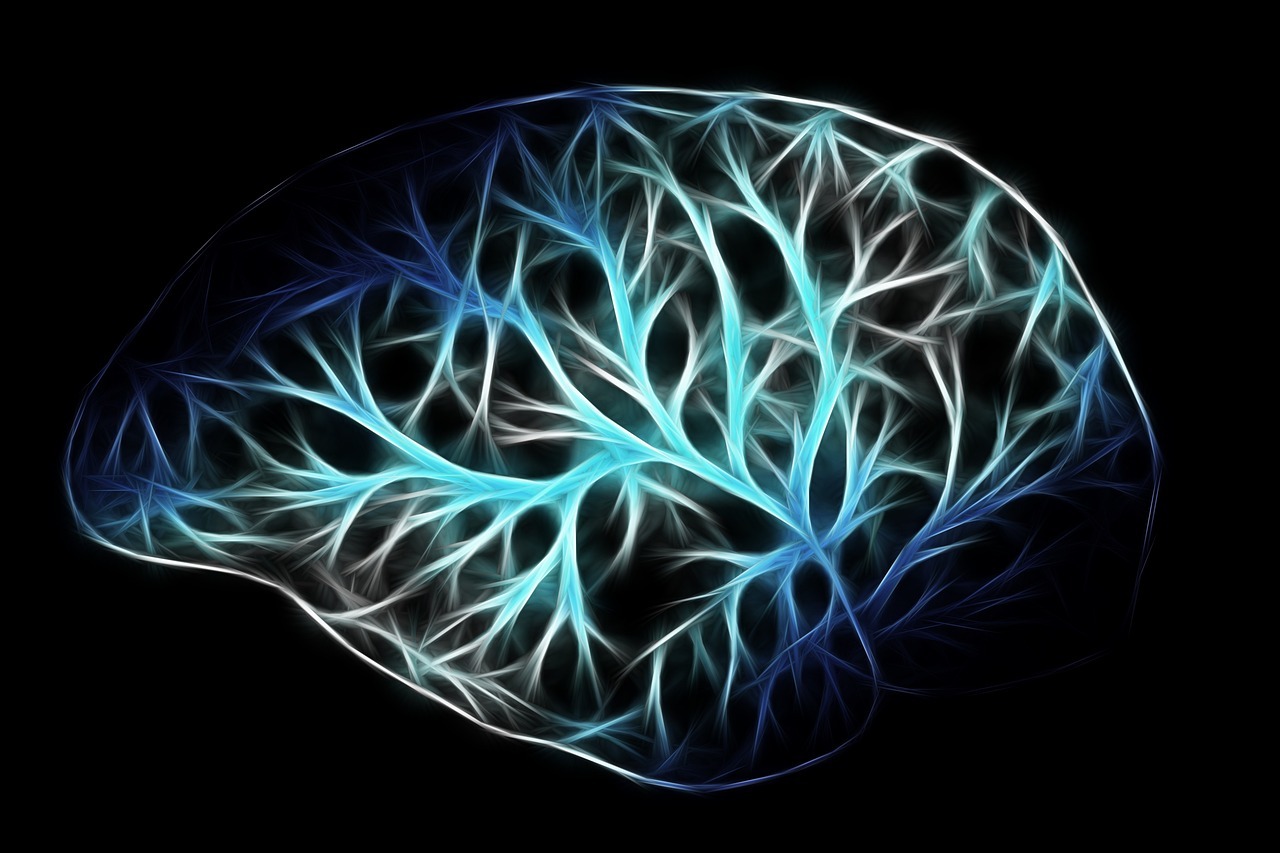
パーキンソン病では、症状の進行により、性格の変化や人格障害が起きることがあります。
ドーパミンの減少・前頭葉や辺縁系の機能低下が原因です。
これらの原因を、詳しくご紹介していきます。
理解しづらい性格の変化を詳しく知ると、病気への理解が深まり受け止められるでしょう。
ドーパミンの減少
パーキンソン病は、脳内で運動を調整する役割を持つドーパミンが減少します。
この影響は、運動機能だけにとどまりません。
なので、感情や思考を司る脳の部位にも変化を及ぼし、パーキンソン病では人格障害が見られることも。
例えば、以前より消極的になったり、怒りっぽい、反対に感情が乏しくなることもあり、ドーパミン減少と深く関わっています。
この症状は、本人の性格が変わったのではなく、脳内の化学的変化によるものです。
病気の仕組みを理解すると適切な対応を取りやすくなると同時に、責める気持ちが減ります。
医療者や専門医との連携は穏やかな日常を保つことが可能となるため、環境やコミュニケーションの工夫を取り入れましょう。
前頭葉・辺縁系の機能低下
パーキンソン病では、脳の前頭葉や辺縁系(へんえんけい)の機能低下が起こることがあります。
判断力や計画性、感情のコントロールを担っているのが前頭葉です。
辺縁系は、脳の内側に位置する海馬・扁桃体・帯状回などが含まれ、主に心の働きを支える中枢ともいわれます。
喜びや不安、恐怖などの感情や記憶に深く関係するこの部位が、うまく働かなくなることで現れるのが以下のような症状です。
- 感情が以前よりも不安定
- 物事への意欲低下
- 性格が変わったように見える
これらの症状は本人の意思、性格の問題ではなく、脳の機能変化によるものです。
パーキンソン病の治療法

ゆっくり進行するパーキンソン病の治療は、薬物療法や手術が基本です。
薬の調整を中心におこないます。
薬を使わず、ストレスを軽減する補助的なストレスフリー療法もあります。
日々の安心につながるので、ぜひ参考にしてください。
薬物治療
パーキンソン病の治療の中心は、脳内の神経伝達物質ドーパミンの不足を補う薬物療法です。
特にレボドパは代表的な薬で、体内でドーパミンに変わり動きのスムーズさ、筋肉のこわばりなどをやわらげる効果が期待できます。
他には、ドーパミンの受容体に働きかける薬や、分解を防ぐ薬です。
患者さんの症状や進行の段階に合わせた処方で薬が調整されます。
薬の効き方や副作用には個人差があるため、医師と相談しながら無理のないよう続けることが大切です。
必要に応じて薬の調整が必要になり、思うように効果が感じられないこともあるかもしれません。
一人で悩まず治療方針を医療スタッフと一緒に考えていくとよいでしょう。
手術療法
薬で十分な効果が得られない場合、手術療法をおこなうこともあり脳深部刺激療法(DBS)の手術が選択肢になることもあります。
手術療法となるのが、パーキンソン病や手や頭が小刻みに震える原因不明の本態性振戦(ほんたいせいしんせん)です。
脳深部刺激療法(DBS)手術では、脳の深い部分に細い電極を埋め込みます。
微弱な電気刺激を与えることで、震えや筋肉のこわばりなどの動きづらさを和らげる方法です。
手術療法は、症状の改善や暮らしやすさが期待できますが、認知機能や精神面への影響も考慮のうえ慎重に判断されます。
パーキンソン病は、人格の変化(人格障害)や精神症状が心配な方もいるため、手術前には十分、医師と相談しましょう。
また、自分の体に合った方法を選び不安を抱えたままで治療を進めないよう、納得できる治療を決めていくのが重要です。
ストレスフリー療法
ストレスフリー療法とは、薬に頼らず体や心に負担をかけない温熱療法です。
研究から得られた究極のツボ4点に、直径3ミリの導子を着け30分から60分ほど、遠赤外線を照射します。
心地よいリズミカルな温熱刺激が、緊張をほぐしてリラックス状態を促します。
不安や緊張が続く方も、無理なく続けられる優しいケアを取り入れていくのもひとつの選択肢。
補助的な方法のため、薬物療法や医師の指導とあわせて取り入れることが重要です。
「銀座数寄屋橋クリニック」はストレスフリー療法に特化した治療を提供しています。
公式サイトにて、詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ

パーキンソン病は、軽い症状から始まり、時間をかけてゆっくりと進行する病気です。
動きの緩慢さや引き込もりにより、認知症や人格障害、幻覚、抑うつなどが現れることがあります。
ドーパミンの減少や脳の機能低下が原因です。
薬物療法や手術療法に加え、薬に頼らない補助的なストレスフリー療法もあります。
医師と相談し、無理なく取り入れてみるのもひとつの選択肢です。






