「今日は動きやすいけれど、昨日はつらかった…」そのような毎日の違いに戸惑うことはありませんか?
そこで今回は、パーキンソン病の進行や日内変動を見つめ直すための、症状日誌の書き方を詳しく説明します。
初期症状や重症度分類(ホーン・ヤール分類)を併せて解説し、心身を整えるストレスフリー療法もご紹介。
症状と上手に付き合っていきたい方や、ご家族を支える立場の方にこそ、参考にしていただきたい内容です。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン病の症状日誌とは
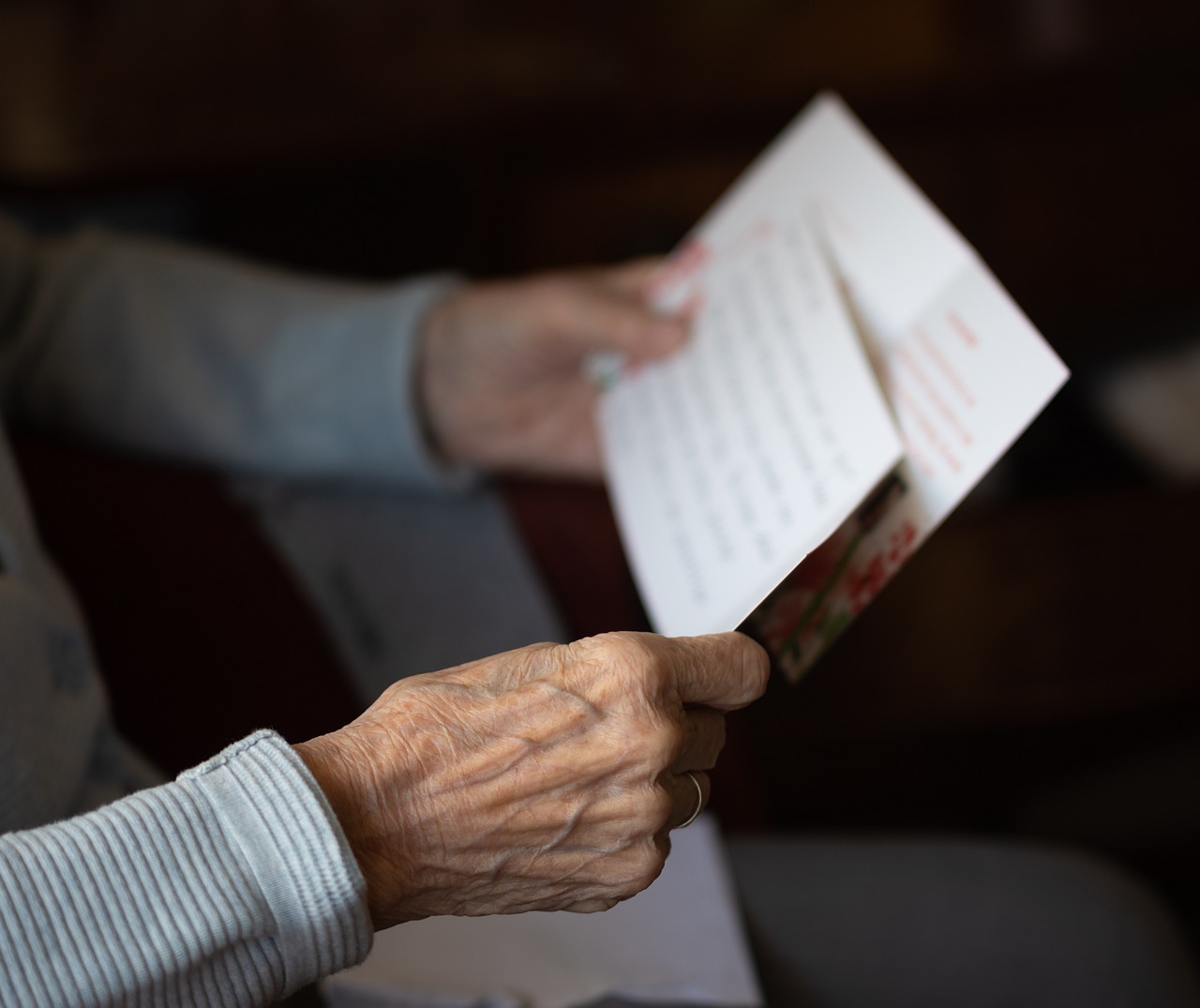
パーキンソン病の症状日誌とは、体調の変化や薬の効き方を時間ごとに記録し、日内変動の把握や治療の見直しに役立てるもの。
主治医や家族との情報共有にもつながり、よりよい日常生活を支える手助けになります。
症状の傾向がわかると、安心して過ごすための工夫もしやすくなり、毎日の暮らしを見直すきっかけにもなるでしょう。
パーキンソン病の症状日誌で記載する内容

パーキンソン病の症状日誌には何を記録すればいいのでしょうか?
症状日誌には、睡眠時間や動かしにくさ、排泄状況、服薬時間、困っていることなどがあります。
そこで、日誌に書いておきたい内容を、詳しくご紹介していくので毎日の気付きを記録するヒントとしてぜひ参考にしてください。
睡眠時間
パーキンソン病では、夜によく眠れない「不眠」と日中の強い眠気の両方が現れることがあります。
このような症状は日ごと、時間帯ごとに変化するため、日誌に睡眠時間や日中の眠気の有無を記録するのがとても重要です。
睡眠のリズムの乱れは、初期の段階から少しずつ進行することも。症状日誌で日内変動のパターンを把握し記録すると、治療や生活リズムの調整に役立ちます。
また、夢のなかで体が動いてしまう「レム睡眠行動異常症」も見逃さず記録するのが大切です。
変化に気付くことで、早めの対応や医師との相談につなげることができます。
睡眠時間は、ご自身やご家族の状態を知る手掛かりにもなるので、記録を続けてみましょう。
動かしにくさ
パーキンソン病では、「身体が動きにくい」と感じる瞬間が日により、あるいは時間帯によって異なることがあります。
そのような変化を把握し、役立つのが症状日誌への記録です。体の動かしやすさ・動かしにくさをこまめに書き残すことで日内変動のパターンを知り、治療や生活の工夫につながります。
動かしにくさの強さや、そのときの気持ちもあわせて記録すると主治医との相談もスムーズになりますね。
パーキンソン病の症状は人により異なるため、ご自身の辛さを記録していくのがとても大切です。
排泄状況
パーキンソン病で多く見られるのは、排尿に関する悩みです。
排尿困難や頻尿、尿失禁などの非尿障害は、病気の進行とともに現れやすく、日常生活や精神的な負担にもつながります。
また、尿道括約筋の運動障害が原因で、自律神経にも影響がでてくるのが、パーキンソン病の進行期です。
具体的には、畜尿に関わる交感神経だけでなく、排尿に関わる副交感神経にも障害が起こります。
そのため、排尿困難への対応が複雑になり、個別の配慮が必要になる場合も。症状日誌には、排泄状況も大切な記録項目のひとつです。
時間帯ごとの排尿の様子、残尿感、急な尿意なども記載しておくと、医師や看護師との相談がスムーズになります。
適切なケアと治療の見直しにもつながるため、特に初期段階からの記録は、進行のサインを早期に把握する手がかりにもなります。
服薬時間
パーキンソン病の治療では、薬を決められた時間に正しく服用することがとても大切です。
特にレボドパのような治療薬は作用時間が短いため、時間をずらしてしまうと血中濃度が下がります。血中濃度の低下は、動作の緩慢さや、震えなどの症状が強く現れることも。
症状日誌には、服薬した時間も記録すると、薬の効き方の変化や日内変動に気付きやすくなり、主治医との相談にも役立ちます。
進行に応じた、適切な治療のために日々の服薬状況も大切な情報として残していきましょう。
困っていること
日々の症状や日常生活での困りごとを症状日誌に記録することがとても大切です。
入浴や食事、立ち上がりなどの動作がいつ、どのように困難だったのか、詳しく書いておきましょう。薬の効果や症状の進行がわかりやすくなります。
特に受診の直前3日間の記録は、医師に相談しやすくなり、伝え忘れを防ぐことにもつながるでしょう。
毎日記録するのが難しい場合は、困った日だけでも構いません。また、小さな気付き(体の動きやすさ・動きづらさなど)もパーキンソン病の治療や支援の見直しに役立つ貴重な情報です。
症状日誌をつける際に参考になるホーン・ヤールの重症度分類

症状日誌をつける際の目安になるのが、パーキンソン病の進行度を5段階で示すホーン・ヤール重症度分類です。
そこで、ご自身の状態を理解する手がかりとしてⅠ度からⅤ度までの特徴を詳しくご紹介していきます。
ぜひ日誌作成の参考にしてください。
Ⅰ度
ホーン・ヤール重症度分類のⅠ度では、パーキンソン病の症状が体の片側に現れます。
主に見られるのは、安静時の震え「安静時振戦」や「筋肉のこわばり」などの、軽い症状です。
動作を始めると和らぐこともあります。日常生活への支障は少なく、仕事や社会活動を続けている方も多い段階です。
症状日誌には、震えの有無や疲れやすさ、気分の変化なども記録していきましょう。
進行の把握や治療の調整に役立つのは、早期の気付きです。
Ⅱ度
パーキンソン病の症状が身体の両側に現れるようになるのが、ホーン・ヤール重症度分類のⅡ度です。
「安静時振戦」が両手足に見られたり、動作がゆっくりになる「無動」や「動作緩慢」が目立つようになります。
動きにくさが日常に影響を与え始めますが、まだ介助は必要ないことが多いです。ですが、家事や仕事で小さな困難を感じる場面も増えてくるかもしれません。
症状日誌には、振戦や疲労感の程度に加え、日常生活で困ったこと(食事や着替えなど)がある場合も記録しましょう。
今後の支援や治療に役立ちます。
Ⅲ度
ホーン・ヤール重症度分類のⅢ度では「姿勢反射障害」が現れ、バランスを取ることが難しくなってきます。
転倒のリスクが高まるのが、歩行中に止まりにくくなったり、後ろに引っ張られると倒れやすくなるなどです。
日常生活には支障が出ますが、まだ介助が必要なレベルではないことも多く、職種によっては仕事を継続されている方もいます。
症状日誌には、転倒の有無や薬の服用前後の変化、薬の効果が切れた際に見られる「ウェアリングオフ」も意識し記録しましょう。
記録は、薬の調整や生活の見直しに役立ちます。
*ウェアリングオフとは、薬の効果が持続しにくくなり、服用の時間が近づくにつれて症状が再び強くなる現象です。
Ⅳ度
ホーン・ヤール重症度分類Ⅳ度では、日常生活のなかで介助が必要になる場面が増えていきます。
歩行や立ち上がりは自力で可能です。
ですが、筋肉のこあばり(筋固縮)や震え、動作の遅れ、バランスの崩れなどが強く現れ、動作全体が不安定になります。
そこで、治療薬に使われるのがレボドパなどです。進行とともに「ウェアリングオフ現象」や「ジスキネジア」が現れることもあります。
症状日誌には、新たに感じた症状にⅢ度で記録していた内容も加えましょう。
介助が必要だった場面や薬の効果の変化なども具体的に記載すると、医師との相談や、治療方針の見直しにも役立ちます。
Ⅴ度
起きたり、歩いたりが一人ではできなくなるのが、ホーン・ヤールの重症度分類Ⅴ度です。
パーキンソン病の症状がさらに進行し、多くの場合、車椅子での移動やベッドで過ごす時間が増えます。
日常生活の場面でも、全面的に介助が必要です。また、末期には「嚥下障害」や「構音障害」などの運動障害に加えて、幻覚や妄想など精神症状が現れることもあります。
他には、認知機能低下や、自律神経障害が現れる場合も。症状日誌には、身体の変化に加え、会話や食事、気分の変化なども記録していくことが大切です。
ご家族の気付きも共有すると、よいケアにつながります。
全身のコンディションを整えるストレスフリー療法

日々のなかで、気分の落ち込みや不眠、疲労感などに悩まされることもあるかもしれません。
そのようなとき、心と体を優しく整える補助的なケアが「ストレスフリー療法」です。
この療法では、直径1.5ミリの導子を着け、30分から60分、遠赤外線の温かな刺激を届けます。医療行為ではありませんが、血流を促し、深いリラックス状態へと導くことを目的とした補助的なケアです。
ご自身の体調に合わせ、心身をいたわるひとつの方法として、無理のない範囲で取り入れてみるのもよいかもしれません。
また、実際の診療実績も多数ありますので、気になる方は実例を参考に検討してみてはいかがでしょうか。
「銀座数寄屋橋クリニック」はストレスフリー療法に特化した治療を提供しています。
公式サイトにて、詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ
パーキンソン病の症状日誌とは、睡眠や動かしにくさ、排泄、服薬、日々の困りごとなどの記録です。
これは、ご自身の変化に気付くための手がかりになるだけでなく、医師との相談にも役立ちます。
重症度の目安に、ホール・ヤーンの重症度分類も参考になりますね。また、医療現場では、主な症状を整理しやすくするため、覚えやすいゴロ合わせが使われることもあります。
そのような工夫を取り入れると、震え・筋こわばり・無動・バランス障害など4大症状の理解や記録にも役立つでしょう。
ストレスフリー療法のような補助的なケアで、心身をいたわるのもひとつの方法です。
記録は、自分を支える力になります。焦らず、ご自身のペースで歩んでいけますように。






