視力が悪いとは、どのような状態なのか疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
視力を改善したい場合、視力が悪くなる原因を知ることが重要です。
この記事では、視力が悪いといわれている状態に加え、視力が悪くなる原因について解説します。
視力が悪くなる原因を知りたい方・さまざまな目の病気の発症リスクが高くなる40代以上の方に、おすすめの内容です。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

視力が悪いと言われる状態

ここでは、視力が悪いといわれる状態のうち、屈折異常・調節異常によるものについて解説します。
目に入った光は、角膜と水晶体で屈折して網膜上に焦点を結び、視神経により信号が送られ脳で映像として認識。
屈折異常とは、目に入った光が網膜上でピントを合わせられない状態です。
近視・遠視・乱視があります。
調節異常とは、ピントを合わせる機能が正常に働かない状態を指します。
老眼が代表的です。
近視
近視とは、外部から入ってきて角膜や水晶体で屈折した平行光線が、網膜より手前で焦点を結んでいる状態。
近くの対象物はピントが合いやすいため、鮮明に見えやすいです。
遠くの対象物はぼやけて見えにくくなるため、注意しましょう。
近視には、以下のものが挙げられます。
- 眼軸長(眼球の奥行き)が正常より長いことが原因の軸性近視
- 角膜や水晶体の屈折力が大きすぎることが原因の屈折性近視
多くは軸性近視とされています。
近視の場合、メガネやコンタクトレンズで視力を矯正する必要があります。
使用されるレンズは、凹レンズです。
遠視
遠視とは、外部から入ってきて角膜や水晶体で屈折した平行光線が、網膜の後ろで焦点を結んでいる状態。
遠視の人は遠くがよく見えると誤解されることが多い点に注意しましょう。
実際は近くの対象物も遠くの対象物も見えにくい状態です。
常にピント合わせが必要なため、調節負荷が大きく、目が疲れやすいといわれています。
遠視には、以下のものが挙げられます。
- 眼軸長が正常より短いことが原因の軸性遠視
- 角膜や水晶体の屈折力が弱いことが原因の屈折性遠視
遠視の場合、メガネやコンタクトレンズで視力を矯正する必要があります。
使用されるレンズは、凸レンズです。
乱視
乱視とは、光を屈折させる角膜や水晶体の歪みにより、目に入る光が1点に集光されない状態。
ものが二重に見える・ぼやけて見えるなどの症状が現れます。
乱視は正乱視・不正乱視に分けられます。
正乱視とは、角膜や水晶体がラグビーボールのような形に歪んでいて、カーブの強さが方向によって異なるため、焦点が網膜上の1点に集まらない状態です。
メガネやコンタクトレンズでの矯正が可能。
不正乱視とは、一般的に角膜が疾患などにより不規則に歪んでいて、光が不規則に屈折する状態です。
ハードコンタクトレンズで矯正できる場合があります。
老眼
老眼とは、加齢によって目の焦点を合わせる力が低下し、近くのものが見えにくくなる調節異常の一種。
人は近くのものを見るときは、水晶体を厚くしてピントを調整しています。
加齢により、水晶体の弾力性が失われ、近くのものにピントが合いにくくなります。
ピントを合わせるための毛様体筋も衰えた結果、老眼に至るため、注意が必要です。
老眼の症状は40代ごろから始まり、徐々に進行します。
細かい文字が読みづらい・違う距離にあるものにピントを合わせるのに時間がかかる・目が疲れやすいなどの症状が現れます。
老眼は眼精疲労の原因にもなるため、老眼鏡・遠近両用コンタクトレンズでの矯正が必要。
視力が悪くなる原因とは一体何か

視力が悪くなる原因には、さまざまなものがあります。
治療しないで放置すると、最終的には失明に至る病気も含まれるため、注意が必要です。
視力が悪くなる原因について詳しく解説していきます。
加齢
老眼は加齢により、誰にでも起こる生理現象のひとつです。
目の調節機能が低下し、近くのものを見るときにピントが合わなくなる状態を指します。
近くの文字が読みにくい・近くから遠く・遠くから近くへとピントを合わせるのに時間がかかるなどの症状があります。
加齢により、白内障や緑内障などの視力の低下を招く病気の罹患率が上昇。
視力が悪くなったと感じた場合、一度眼科を受診しましょう。
目の酷使
目の酷使による疲れ目・眼精疲労も視力が悪くなる原因です。
疲れ目とは、目を使い続けることで、目の痛み・かすみ・まぶしさ・充血などが現れた状態を指します。
眼精疲労とは、目の症状だけでなく頭痛・肩こり・吐き気などの全身症状が現れ、休息や睡眠をとっても十分に回復しない状態。
疲れ目は休息や睡眠をとると回復しますが、放っておくと眼精疲労に進展するといわれています。
近年は、スマートフォンやパソコンの長時間使用により、疲れ目や眼精疲労に悩まされている人が多いです。
白内障
白内障とは、加齢や紫外線、糖尿病などの原因により、目の水晶体が濁る病気です。
水晶体はカメラのレンズのように外からの光を集め、ピントを合わせています。
水晶体が濁ると、光が通りにくくなり、ピント調整機能が低下。
結果、目のかすみ・光がまぶしい・視力低下・ものが二重に見えるなどの症状が現れます。
早い人では40代で発症します。
80歳を過ぎると、ほぼすべての人に症状が認められるため、注意が必要です。
初期は進行抑制目的で点眼薬で治療を進めます。
進行した後、視力回復目的で濁った水晶体を眼内レンズに交換する手術をおこないます。
網膜剥離
網膜剥離とは、網膜に裂孔ができ、そこから徐々に網膜が剥がれることで視力の低下を生じる病気。
黒い点が飛んでいるように見える飛蚊症・光がチラチラ見える光視症・視野欠損などの症状が現れます。
網膜が剥離すると、その部分の視細胞は酸素や栄養を受け取れず機能を失うため、できるだけ早い段階での治療が必要です。
文字などを認識する黄斑部が剥離すると、短期間で大幅な視力低下を起こします。
網膜裂孔に対しては、剥離を抑えるためのレーザー治療をおこないます。
剥離が認められる場合、手術が必要です。
ぶどう膜炎
ぶどう膜とは、眼球を包む脈絡膜・毛様体・虹彩から構成され、血管と色素に富んだ組織となっています。
ぶどう膜炎は、ぶどう膜に炎症が起こる病気。
細菌・ウイルス・真菌などによる感染や免疫異常などが原因です。
目の痛みやかゆみ、視界のかすみ、まぶしさを強く感じる、飛蚊症などの症状を起こします。
原因に合わせた治療がおこなわれます。
再発しやすい点に注意しましょう。
治ってからも定期的に受診する必要があります。
緑内障
緑内障は、視神経の障害により視野が狭くなっていく病気です。
損傷した視神経を元に戻す方法はなく、失明のリスクを伴います。
眼球の中に房水が流れており、房水の流れにより発生する眼球内部の圧力が眼圧。
眼圧が上昇すると、眼底にある視神経乳頭が圧迫されます。
視神経が損傷することで、視野の一部が欠損します。
初期症状はほぼ自覚されないことが多いのです。
目のかすみ・視力低下などの違和感があれば、できるだけ早く眼科を受診しましょう。
早期発見し治療を開始すれば、視野障害の影響を抑え、通常の日常生活に戻ることが十分可能です。
黄斑前膜
黄斑前膜とは、網膜の中心にある黄斑部の前面に薄い膜が張る病気。
網膜の疾患の中では最も発症数が多く、40歳以上の20人に1人が発症するといわれています。
初期には自覚症状がほぼありません。
進行すると、膜が収縮して網膜がむくんでシワができます。
ものが歪んで見えるなど、視力に影響を及ぼすため、注意が必要です。
一般的に、眼球の中の硝子体は加齢に伴い収縮して網膜から離れていきます。
その過程で網膜の表面に残った硝子体により、膜を形成することが原因。
黄斑前膜は緩やかに進行する場合が多く、失明の危険性が少ない点が特徴に挙げられます。
定期検査による経過観察をすることが多いです。
糖尿病
糖尿病により視力が低下する主な原因は、糖尿病網膜症によるものです。
初期は自覚症状が少なく、進行すると飛蚊症や視力低下などが見られます。
最終的には、失明に至る場合もあります。
高血糖状態が続くと、網膜の細い血管が損傷を受け詰まりやすくなるため、注意が必要。
網膜全体に酸素が行き渡らず、新生血管を作って酸素不足を補おうとします。
新生血管は脆く容易に出血を起こした結果、網膜剥離を起こすことがあります。
治療法はレーザー光凝固術・硝子体手術などです。
糖尿病性白内障も視力低下につながる糖尿病の合併症。
日常生活において白内障などを対策することが重要

日常生活において、白内障などの目の病気の予防を心掛けることが重要です。
目の病気の予防法としては、バランスの取れた食事や紫外線対策、目の休息、定期的な眼科検診などがあります。
特に、ビタミンC・ベータカロチン・ルテインなどの抗酸化成分を豊富に含む食品を摂ることで、目の健康をサポートできます。
サングラスによる紫外線対策・パソコンやスマホの長時間使用を避けることも大切です。
40歳を過ぎたら、年に一度の眼科検診を受けることもおすすめします。
目のコンディションをサポートするストレスフリー療法

近年、全身の血流や自律神経を整えて目のコンディションを根本からサポートするストレスフリー療法が注目されています。
ストレスフリー療法とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30~60分照射する温熱療法。
ストレスホルモンの低減・血流の大幅な増加などの効果が確認されています。
高血圧や糖尿病、認知症、不眠症、冷え症など、さまざまな病気の症状を改善する効果が期待できます。
ストレス低減・血流改善により、見え方の改善効果にも期待ができる点もポイントです。
ストレスフリー療法を受けたことにより、白内障などの目の疾患の改善効果があった報告もあります。
当療法に特化した専門クリニックとして信頼されているのが、「銀座数寄屋橋クリニック」です。
公式サイトにてさらに詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ
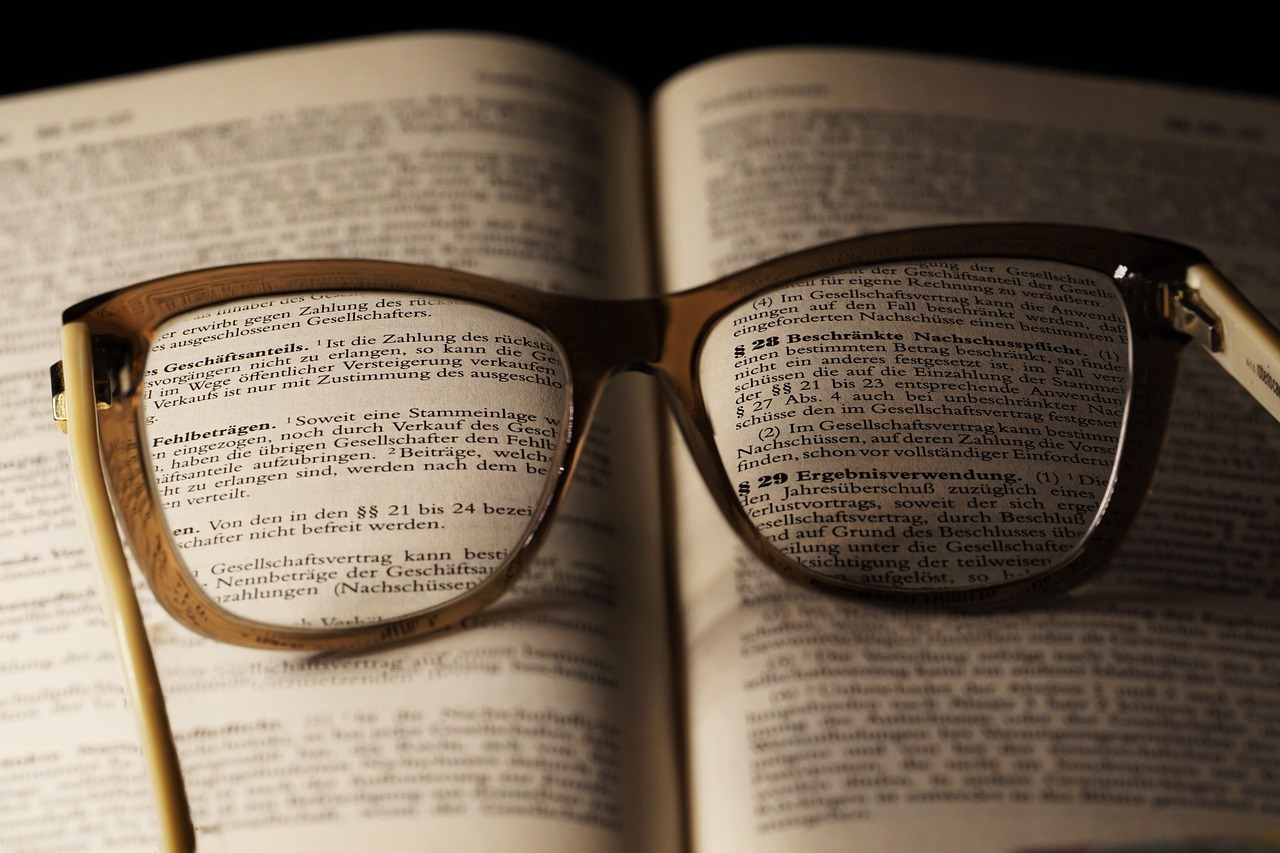
今回は、視力が悪い原因について詳しく解説しました。
視力が悪いといわれる状態には、屈折異常(近視・遠視・乱視)・調節異常(老眼)が挙げられます。
メガネなどで視力を矯正する必要があります。
視力が悪くなる原因には、加齢や目の疲労のほか、白内障や緑内障などの病気の可能性がある点に注意が必要。
病気が原因の場合、放置しておくと失明につながることもあるため、早めに眼科を受診することが重要です。
目の病気を予防する方法の一つとして、ストレスフリー療法が挙げられます。
この記事が、視力が悪くなったことで悩んでいる方の参考になり、白内障などの病気の早期発見につながれば幸いです。






