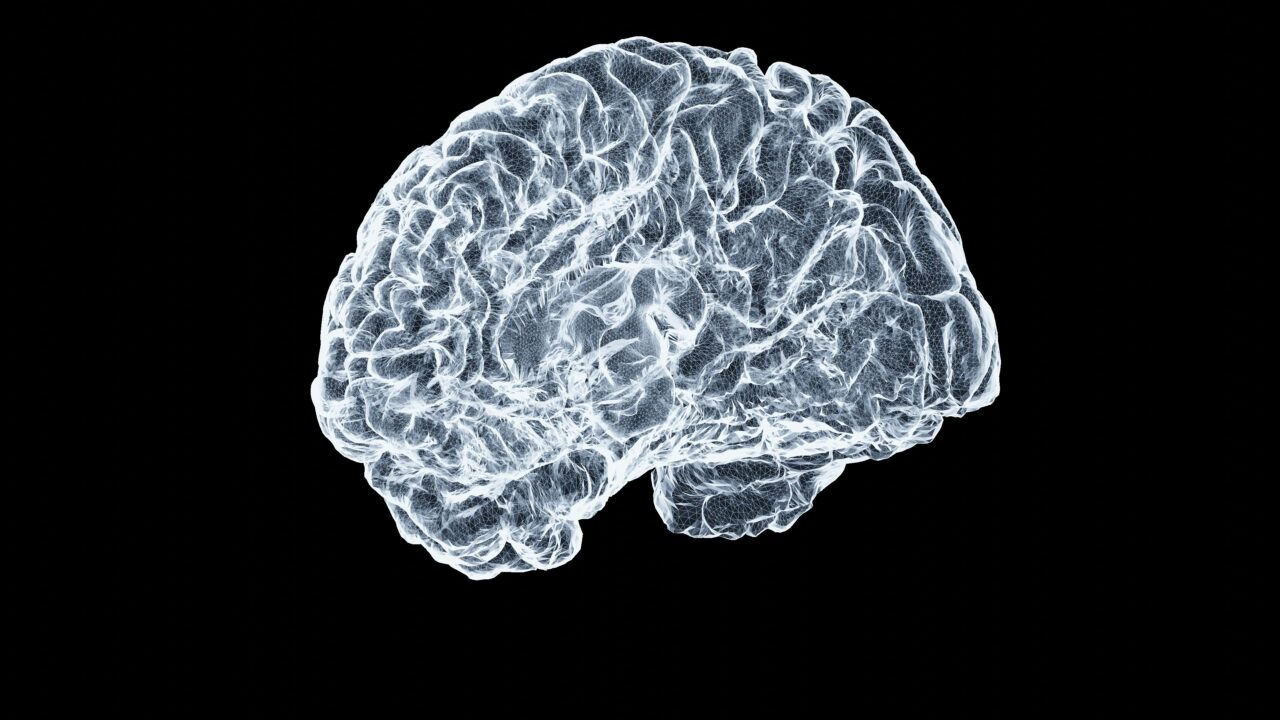足がもつれる、手足が震えるなどのパーキンソン病にみられる症状は、他の病気にも共通する症状です。実はパーキンソン病だと思っても違う病気だったなんてこともあります。今回はパーキンソン病に似ている病気と見分ける方法を紹介します。

監修者:佐藤琢紀(サトウ タクノリ)
銀座数寄屋橋クリニック院長
2004年東北大学医学部卒業後、国立国際医療センターで研修医として入職。2019年には国立国際医療研究センター国府台病院救急科診療科長に就任。18年間救急医として約36,000人の診療経験を通じ、現行医療の限界を認識。元氣で楽しい人生を歩むための戦略の重要性を感じる中、ストレスフリー療法と出会い、その効果に感銘を受ける。これを多くの人に広めるべく、2024年4月より銀座数寄屋橋クリニックでストレスフリー療法に特化した診療を行っている。
銀座数寄屋橋クリニックはこちら。

パーキンソン病とは一体どんな病気なのか
パーキンソン病は脳から放出されるドーパミンが減少して、運動の調節機能がうまく働かず、体の動きに障害があらわれる病気です。
何年もかけてゆっくりと進行する病気で、手足が震えたり、バランスが取れなかったり日常生活に支障をきたします。
他にもドーパミンの減少は自律神経や中枢神経にも影響を及ぼし、便秘や抑うつ症状、認知症などの症状があります。
ドーパミンが減少する原因ははっきりとは解明されていませんが、ほとんどが遺伝ではなく、孤発性です。
パーキンソン病に似た病気
パーキンソン病と同じような症状がみられる病気はいくつかあります。
脳疾患や神経系の病気など、パーキンソン病に似た症状が出る病気を紹介します。
進行性核上性麻痺
進行性核上性麻痺とは脳の中の神経細胞が減少して、転びやすくなったり、下のほうが見にくくなったり、しゃべりにくい、飲み込みにくいなどの症状が現れる病気です。
初期の頃はパーキンソン病の症状に似ていて区別がつきにくいですが、パーキンソン病の治療薬があまり効かず、効果があっても一時的な場合が多い疾患です。
神経細胞にタウタンパク質というタンパク質が蓄積するのが原因ですが、蓄積する理由は解明されていません。
大脳皮質基底核変性症
大脳皮質基底核変性症はパーキンソン病と大脳皮質症状が同時に現れる病気です。脳の神経細胞が脱落し、残った神経細胞への異常なタンパク質の蓄積が原因といわれています。
まだはっきりとした原因は解明されておらず、稀な疾患です。
始めは左右どちらか一方が思うように動かせなくなり、次第に両足にも障害が起こり、5〜10年で寝たきりになる人がほとんどです。
頭部CTやMRI検査をして、前頭葉と頭頂葉の萎縮に左右差があれば、大脳皮質基底核変性症と確定します。
多系統萎縮症
多系統萎縮症は、小脳や自律神経など複数の神経系に障害を起こす進行性の神経難病の1つです。
小脳の障害でふらつきや歩行困難が、パーキンソン症状でふるえや筋肉のこわばりなどの症状がでます。
さらに自律神経障害も起こり、便秘や発汗異常などの症状もあります。脳の細胞にαシヌクレインというタンパク質が異常に蓄積し、小脳や脳幹が萎縮してしまうのが原因です。
平均余命は診断後5〜9年で、最終的に運動機能が失われ呼吸不全や心停止により亡くなってしまいます。
ギランバレー症候群
ギランバレー症候群は末梢神経障害により急に手や足に力が入らなくなる病気です。
10万人に1人と稀な病気で、子供から老人まで発症する可能性があります。
風邪や下痢をきっかけに発症し、2〜4週間以内に症状ピークに達します。
免疫システムの異常が原因で、適切な治療を受ければ6〜12ヵ月で回復できる病気です。
しかし、約20%の人には後遺症が残り、重症化すると人工呼吸器なども必要になってくるので、早めの治療が大切です。
レビー小体型認知症
レビー小体型認知症はアルツハイマー型認知症についで2番目に多い認知症です。
レビー小体というたんぱく質が蓄積した脳の神経細胞は、機能を失います。
レビー小体が出現する理由はわかっておらず、神経細胞の減少により認知機能障害やパーキンソン病の症状が現れます。
ほかにも幻想を繰り返し見るなどの特徴があります。
初期症状に認知機能の低下は認められませんが、検査をして脳の血流低下が見られたら診断が確定します。
パーキンソン病かどうか見極めるポイント
パーキンソン病の症状と似た病気がさまざまありますが、他の病気と区別されるには理由があります。
どのように違いで見極めたらよいのか解説します。
症状の進行速度がどのくらいか
パーキンソン病はゆっくりと症状が進行します。
パーキンソン病患者の平均寿命は健常者と大きく変わらないといわれていますが、パーキンソン病に似た病気のなかには、進行が早いものもあります。
また、初期にパーキンソン病の症状が出るのは、左右どちらか一方が一般的です。
症状が左右対称だったり、極端な違いがある場合は他の疾患の可能性があります。
パーキンソン病治療薬の効き目
パーキンソン病と他の疾患の区別が難しいときは、薬を服用してもらい効果がみられるかで判断します。
パーキンソン病は脳からのドーパミンが減少して運動機能障害を引き起こします。
そのドーパミンを補充する薬がパーキンソン病の治療薬のメインになりますが、パーキンソン病ではない場合、症状の改善がみられません。
もし症状が改善されても一時的な場合もあるので、治療薬の効き目でパーキンソン病かどうかを判断します。
脳血管の様子
MRI画像検査をおこない、ドーパミンを放出する中脳の黒質が萎縮していたらパーキンソン病の可能性があります。
またパーキンソン病でドーパミン神経細胞が壊れると脳の中のドーパミン量を調節しているドパミントランスポーターが減少するため、その変化をSPECT検査で確認します。
ただし、パーキンソン病はMRIなどでの確定が難しいと言われており、逆に他の部位に萎縮や異常がみられた場合は、パーキンソン病以外の病気の可能性が高いです。
認知症の併発時期はいつか
パーキンソン病の症状の1つに認知症がありますが、発症するのは70歳以降で、診断から約10〜15年と言われています。
逆に初期から認知症の症状が認められる場合は、パーキンソン病ではない可能性が高いです。
パーキンソン症状を併発するレビー小体認知症も、始めは認知機能障害が認められるのが特徴です。
パーキンソン病は診断確定できる検査がないため判断が難しいといわれていますが、症状の併発時期から疾患を判断します。
全身のコンディションを整えるストレスフリー療法

ストレスフリー療法とは、身体の特定の6点に直径1cmの導子をつけ、遠赤外線を30〜60分照射する温熱療法です。
血流の向上により、冷え性や睡眠障害が改善されます。パーキンソン病はドーパミンの欠乏が原因と考えられていますが、脳への血流改善によってドーパミン生成が促され、症状が改善した例もあります。
またストレスフリー療法はドーパミン減少の原因であるストレスホルモンのコルチゾールを低下させる効果があり、パーキンソン病の予防にも役立つと考えられています。
当療法に特化した専門クリニックとして信頼されているのが、「銀座数寄屋橋クリニック」です。
公式サイトにてさらに詳しい情報をご覧いただけます。
まとめ
パーキンソン病に似た病気は数多くあり、判断が難しい場合もあります。
完全に原因が解明されていない難病に分類わけされる病気もありますが、いずれも早期の治療が大切です。
ストレスフリー療法は、全身の血流改善が期待でき、パーキンソン病の症状が改善した例もある近年注目されている治療法です。
ストレスホルモンを低下させる効果があり、体の不調を整える効果があります。